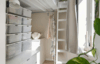粗利率を改善する!工務店の収益性向上策
公開日:
:
最終更新日:2025/10/28
工務店 経営
工務店を経営されている多くの方が、「利益が思うように増えない」「粗利率がなぜか低い」といった悩みを抱えていらっしゃいます。長引く資材価格の高騰、人件費や外注費の増加、厳しくなる受注競争……。こうした状況では、ただ売上を伸ばすだけでは会社の成長は頭打ちになりがちです。本記事では、まさに今、多くの工務店に必要とされている利益改善の本質と、具体的な粗利率アップの手法にフォーカスします。どんな業務改善を行えばよいのか、数字をどう見直せばよいか、すぐ行動できる実践策をお伝えし、明日から会社の収益性を高める具体的な一歩を踏み出せるようアドバイスいたします。「今のやり方で本当に良いのか」と疑問を感じている経営者の方に、この記事から確かなヒントをお約束します。
粗利率の「実践的」導入戦略:基礎から応用まで
まずは「粗利率」とは何か、また、それがなぜ工務店の利益改善に直結するのかを明確に理解しましょう。その上で、自社に最適な粗利率目標設定の仕方や、経営現場で即活かせる導入アクションについて、具体的なステップで解説します。
STEP1. 粗利率の基本を正しく押さえる
- 粗利率=(売上高-原価)÷売上高×100(%)で算出します。建築業の場合、原価には「資材費」「外注費」「直接人件費」などが該当します。
- この数値は、「受注した仕事がどれだけ会社の利益になっているか」を端的に示す指標です。売上至上主義になってしまうと、受注量が増えても原価が膨らみ、最終的な利益が薄まるリスクがあります。
STEP2. 現状分析で自社の「ムダ」を洗い出す
- まずは直近1~2年分の全案件を振り返り、案件ごとの粗利率を把握します。利益が出ている案件、逆に薄利赤字になった案件の特徴を書き出しましょう。
- この際、見積もり時点と実績値の粗利率の違いも細かく記録します。設計変更や材料ロス、予想以上の外注費増加など、どこで粗利率が崩れたのか原因を丁寧に特定してください。
STEP3. 目標粗利率の設定と全社共有
- 業態やエリアにもよりますが、多くの工務店が目標とする粗利率は20~30%と言われます。自社の現実的な現状を踏まえ、まずは「あと1%、2%上げる」など小さな目標を段階的に設けるのが現実的です。
- 設定した目標粗利率は経営者だけでなく、営業、現場、設計など各部署と共有して初めて意味を持ちます。定例会議などの場で数値目標を「見える化」し、一丸となって取り組む体制を作りましょう。
STEP4. 実践のための業務見直し「3つの視点」
- ①見積もり精度向上:利益を生み出す第一歩は、正確な見積もりから始まります。過去案件の報告書や仕入れ明細を徹底的に洗い直し、価格改定や外注手当の反映漏れがないかチェックしましょう。
- ②原価管理:各案件ごとに原価管理表を整備し、現場ごと・月単位で予実管理を徹底してください。数字の把握を「現場任せ」にせず、経営層が定期レビューする仕組みを作ることが要です。
- ③変更管理:顧客要望による設計変更や追加工事の発生時は、後回しにせず即見積もり変更・契約変更を行います。曖昧な口約束は粗利率低下の最大要因になるため、施工前に必ず正式な手続きを取りましょう。
STEP5. 社内教育・現場意識改革に投資する
- 粗利率は「経営者・役員だけが考えるもの」と捉えられがちですが、現場と一体にならなければ意味がありません。積算担当や現場管理者に対し、粗利率がどうして重要なのか説明し、価値観を共有しましょう。
- 「少しの油断や値引きが、会社全体の利益にどれだけ影響するか」を実データで示すと、理解が進みます。また、粗利率向上に貢献した社員を評価・表彰するなど、行動を促す仕掛けづくりが有効です。
利益改善×粗利率:成果を最大化する具体的な取り組み
粗利率を向上させ、利益改善を実現するためには「現場改善」「仕入れ交渉」「業務フロー見直し」「社内コミュニケーション」など、複数分野のアプローチが必要不可欠です。ここでは、工務店で高い成果を上げている実践例と、よく寄せられる疑問・不安への明快な回答を組み合わせて解説します。
1. 仕入れ・外注費のコントロールで粗利率を底上げ
- 主要資材や外注費は、一定期間ごと(3ヶ月や半年ごと)に価格交渉を行いましょう。特定の仕入先任せ、協力会社任せではなく、複数業者と比較してコスト競争力を維持します。
- 「値引き交渉が難しい」と感じる場合は、注文頻度や施工実績のシェア拡大を材料に、“Win-Win”の長期的な関係性を強調して交渉に臨むと効果的です。
- 共通材料は複数現場でのまとめ買いや、標準仕様への共通化なども検討しましょう。
2. 工程管理の徹底によるロス排除・機会損失防止
- 納期遅延や手戻り(やり直し)はすべてムダなコスト=粗利率低下の原因です。工期表・ガントチャートを駆使し、材料納品・外注手配・工程進捗を全員でリアルタイムに共有しましょう。
- 小規模工務店でもExcelや無料の工程管理アプリを活用し、見える化を推進してください。現場ごとの「遅れ理由」を定期的に分析し、再発防止策までセットで実施することが利益改善の近道です。
3. 残業・やり直しの抑制で間接コストを削減
- 繁忙期の残業増加や、図面ミス・指示間違いによるやり直し作業は、“見えない赤字”として累積します。デジタル化(タブレットでの現場指示、図面のクラウド共有等)を進め、オペレーションコストを下げましょう。
- 定例会議等で「今月のムダ・やり直し事例」を共有し、小さな改善提案を積み重ねることで全体業務の質を高められます。
4. 付加価値提案による単価アップ戦略
- 単純な値引き営業から脱却し、「長期保証」「高機能断熱材」「デザイン提案」など、顧客ごとのニーズに合わせてアップセルを提案することで、商談あたりの単価アップ=利益改善に直結します。
- 仕様変更やグレードアップの提案は、タイミング(契約直後や設計初期段階)と説明力がポイント。スタッフに「価値を伝えるセールストーク」をロールプレイングで教育するのも効果的です。
5. 営業活動と収支管理の連携強化
- 営業担当者に、単に「受注数」だけでなく、「粗利率の意識」を持ってもらうことが不可欠です。見積前には経営陣が粗利シミュレーションを共有し、コスト想定から逸脱していないかを細かくチェックしましょう。
- 営業・設計・現場管理の各部門が一体で動き、契約獲得後の「引き継ぎミス」「仕様確認の抜け漏れ」をゼロにすることで、無駄なマイナスを防げます。
よくある質問(FAQ)とピンポイント回答
- Q1. 具体的に毎月確認すべき「利益改善」行動は?
毎月一度、「今月の粗利率と赤字案件」「資材明細・外注費の内訳」「現場から上がったコスト増要因」などを短時間でレビューし、次月の仕入れ・業務変更点を即意思決定することです。迅速なPDCAが重要です。
- Q2. 目標粗利率が届かない時、どこを見直すべき?
まずは見積もり精度、次に原価管理表の正確さ、さらに案件ごとの変更点(設計変更・追加工事)の対応遅れを優先的に精査します。各案件で「何が突発要因だったか」を明文化し、再発防止策を作ってください。
- Q3. 原価把握はどう進めたら社内で定着しますか?
経営陣が毎月「原価管理表」をチェック・共有する習慣を作り、現場メンバーにも一覧で見せることから始めます。「感覚」でなく「実数値」での会話を繰り返すことで、会社全体の意識改革が進みます。
利益改善を継続的に成功させるための「次の一手」
一時的に粗利率や利益改善が進んだとしても、「継続」「仕組み化」しなければ将来的な安定成長にはつながりません。このセクションでは、中長期での利益改善定着、見える化、組織力強化の方法と、より高いレベルへ進むための戦略的アクションをまとめます。
STEP1. 毎月・四半期ごとの業績モニタリング体制を整える
- 売上・粗利率・販管費などの経営指標を、毎月定例で「見える化」し、役員・管理職・現場リーダーが全員でチェックできる環境づくりをします。
- 前年同月や直近3~6か月との推移も継続的に比較することで、「利益改善の成果」「次に手を打つべき課題」の両方を明確化できるようになります。
STEP2. デジタルツールで業務標準化・ブラックボックス撲滅へ
- 現場別の原価管理、営業集計、工程進捗などは、Excelからクラウド会計・工程管理アプリ(アンドパッドや建築業専用ソフト等)への移行を進めましょう。入力・集計の自動化により、ミスや抜け漏れが大幅に削減されます。
- 各現場・各担当者の数字が全社で見えるようにすれば、「属人化」による利益のムラを最小化することができます。
STEP3. 社外・業界ネットワークの活用で情報力アップ
- 同業他社や業界団体での情報交換会に定期的に参加し、「隣の工務店はどのくらい利益改善できているか」「新しい仕入・原価管理手法がないか」を積極的にキャッチアップしましょう。
- 外部専門家(税理士、中小企業診断士、ファイナンシャルプランナーなど)への定期相談も、経営判断の幅を広げる有力な材料になります。
STEP4. 人材育成と評価制度による組織力向上
- 粗利率や利益改善に寄与した提案・達成行動が、正当に評価・昇給・表彰される制度を設計しましょう。「できる人だけが頑張る」から「全員が参加する」会社文化への転換が必要です。
- 社内勉強会やオープンな会議で、「利益改善の成功事例」「失敗事例」両方を共有し、トライ&エラーを許容する風土を育てることが、中長期での差につながります。
STEP5. 新分野・サービスへの展開を検討する
- 築古住宅のリフォーム、設備更新、太陽光や省エネリノベなど新しい分野での受注開拓は、従来の「利益が伸びない」状態から脱却する重要施策です。
- 施工標準化・パッケージ化できるメニューを増やし、都度見積もりから「利益確保のしやすい」提案型商品開発に踏み込みましょう。
まとめ
工務店の収益構造を強くし、利益改善を持続するための実践策は、単なるコストカットや営業強化だけではありません。粗利率の基礎理解と目標設定から始め、業務フローや原価・工程管理、スタッフ育成全体でアクションを重ねてこそ、確かな利益改善が実現します。また、業務の属人化排除・情報の見える化による継続的なモニタリングや、組織的に人材を評価する仕組みづくりも欠かせません。小さな「できること」から一つずつ着実に取り組むことで、会社全体の利益体質が強固なものになります。今日から実行できるアクションを実直に継続し、数ヶ月後・数年後の更なる成長につなげてください。皆さまの経営がより力強く、未来志向で発展していくことを心から応援しています。
工務店の集客・営業ならジーレックスジャパン →ホームページはこちら
商品の差別化へ!制振装置はこちらから →耐震・制振装置
友達申請お待ちしてます! →代表浄法寺のfacebook
工務店のネット集客ならこちら →工務店情報サイト ハウジングバザール
関連記事
-

-
イベント開催で新規顧客獲得!工務店のノウハウ
2025/09/18 |
工務店を取り巻く市場環境は近年大きく変化しており、「新規顧客がなかなか獲得できない」「リピーターが増...
-

-
イベントを通じて見込み客を優良顧客に育成する方法
2025/08/20 |
工務店経営において、「新規顧客をどう獲得し、どうリピーターやファンに育てていくか」は永遠の課題です。...
-

-
工務店 経営 軽のスズキが最大の危機から脱した思考
2023/05/09 |
最近は軽自動車がとても多いですよね。 かくいう私も乗っています。 その中でも大きい売り上...
-

-
データに基づいた経営判断!工務店の課題解決に繋げる
2025/07/18 |
工務店を経営していると、「今のやり方で本当に利益が出るのか」「次にどんな一手を打つべきか」など、さま...