売上高を増やす!工務店の営業戦略
公開日:
:
工務店 経営
工務店経営において、「利益改善」と「売上高の増加」は避けては通れない最重要テーマです。特に近年は資材高騰や人材不足、競合の激化など、多くの工務店が「忙しいのに手元に残らない」「売上高は伸びているのに利益が思ったほど増えない」といった悩みに直面しています。本記事では、こうした課題にどう立ち向かい、誰でもすぐに始められる具体的なステップと、現場で実践できる営業戦略を徹底解説します。単なる売上高アップだけでなく、「継続的な利益改善」に直結する本質的な仕組みづくり、日々の業務改善手法まで深掘りし、読者の皆さんが「明日から何をやれば利益が変わるのか」を明確に理解し、確信を持ってスタートできる内容になっています。今悩んでいる方も、これから事業拡大を目指す方も、今日から取り組める確かな行動指針を手に入れてください。
売上高の「実践的」導入戦略:基礎から応用まで
工務店が利益改善を実現するための第一歩は、売上高を安易に追うのではなく、「収益性の高い売上」をどれだけ積み上げられるかにあります。ここでは、利益改善と売上高増加双方に寄与する具体的な営業戦略をステップ形式で解説します。
1. 市場分析とターゲット設定を明確にする
まず、自社の現状を「見える化」することが何より大切です。ただ闇雲に新規受注を増やしても、粗利率が低い案件ばかりでは利益改善にはつながりません。地域や工事種別ごとの需要変動、競合状況、自社の得意分野(例えばリフォーム、注文住宅、小規模修繕など)を洗い出し、最も利益貢献度の高いセグメントに狙いを絞りましょう。
- 売上高と利益率を現状把握(Excelや業務管理ソフトで直近1〜2年分を集計)
- 過去の受注案件を分類し、利益貢献度上位の案件の特性(客層、エリア、工事内容)を分析
- 狙う市場(ターゲットセグメント)を明文化し、全社で共有
2. 商品・サービスの「強み」と「収益性」を棚卸しする
利益改善のためには、自社が本当に得意とする商品・サービスにリソースを集中投下し、コモディティ化した案件や赤字リスクの高い受注は減らす決断も重要です。また、競合と差別化できる独自性(事例提案、保証体制、迅速対応など)を明示することで、価格競争からの脱却と顧客単価アップを図ります。
- 自社の主要サービス・商品ごとの利益率、手間・工数を一覧化
- 「競合が真似できない独自要素」「顧客への明確なベネフィット」を整理
- 利益性の低い商品の見直し・廃止、販売強化すべき商品の決定
3. 価格戦略の再設計で収益構造を変える
単なる割引や値下げではなく、「価値提案型」の価格戦略が利益改善の大きな鍵となります。自社の強みを活かした「付加価値パッケージ」「アフター保証込みパック」「即対応オプション」などを設計し、値引きではなく価値で選ばれる営業提案を全社的に徹底しましょう。
- 値引き額・割合や値引き条件をあらためて標準化し、営業現場の裁量を制限
- 高付加価値メニュー(例:長期保証、定期点検、エコリフォーム追加)を明文化
- 顧客の「不満ポイント(価格以外)」を調査し、そこを解決する独自サービスで単価を底上げ
4. 受注確度を高める「見積・商談プロセス」の改善
利益改善の決め手は、「取るべき案件を確実に受注し、取るべきでない案件は見極める」判断軸を組織全体で持つことです。商談プロセスの標準化と見積フォーマット見直しにより、属人化(担当者の経験や思い込みに左右されること)を排除できます。
- 見積作成基準・利益率目標を全営業に周知し、徹底させる
- 見積~受注までの主要ステップ(課題ヒアリング、現地調査、ベストプラン提案、クロージング)をフローチャート化
- 営業会議の議事録や進捗管理で、利益率低下の要因をその都度レビュー
5. 顧客管理・再受注戦略の構築
新規受注だけで売上高を伸ばそうとしても、コスト・手間ばかり先行し利益改善が難しくなります。既存顧客へのリピート提案、定期点検・フォロー訪問を仕組み化し、「貯める営業」から「回す営業」への転換が欠かせません。
- 顧客リストを整備し、リフォーム周期や誕生日などで自動的にアプローチできる体制を整備
- 「5年点検はがき」「住まいの健康診断」など既存顧客向けキャンペーンを毎月企画
- 初回取引からのLTV(顧客生涯価値)を算出し、再受注率UP目標を掲げる
以上の導入策を、状況に合わせて少しずつでも着実に実行することで、工務店の「単なる売上高増加」から「持続的な利益改善」へ確かな一歩を進めることができます。
利益改善×売上高:成果を最大化する具体的な取り組み
ここからは、利益改善と売上高最大化の両輪を実現するためのより具体的な現場施策および、よくある疑問・課題への解決策を交えて解説します。実務で即実行可能なアクションプランとして参考にしてください。
1. 案件ごとの「利益管理体制」を徹底する
案件ごとの粗利益・実利益を見える化できていますか? 利益改善の基本は「漏れなく・素早く」原価、経費、粗利を把握し、危険な案件は即座に手当てできる体制です。これが「判断できる組織」を作る礎となります。
- 受注時、見積もり段階から「実行予算書」を必ず作成し、標準粗利率を下回る案件は上長承認を徹底
- 現場材料費・外注費・人件費の集計をできる限りリアルタイムで行う(クラウドサービスやExcel自動化を活用)
- 工事終了後に「実績原価」と「見積原価」の差異分析(利益改善会議の定例化)
2. 原価低減・仕入先交渉力を強化する
原材料費、人件費、外注先コストの削減は今や全ての工務店の命題です。ただし「安ければ良い」「締め付け強化」だけでは現場力が低下しがちなので、建設的な協力関係を築きながら原価低減を図る仕組みが不可欠です。
- 仕入先・外注先ごとに主要コストを一覧化し、定期的に相見積もり方式を導入
- 「年間取引量に応じた価格改定」「納期短縮」「品質保証」などWin-Winの交渉ポイントを設定
- 廃棄・ロス材在庫の削減も大きな利益改善につながる(半端材活用キャンペーンなど)
3. 業務プロセスの自動化・標準化で無駄を省く
「業務が忙しい=利益が増える」とは限りません。現場調査、見積作成、契約事務、現場管理などの定型業務は、極力標準化・自動化して、繁忙期のボトルネックや属人化を排除します。その余剰リソースを「高付加価値営業」や「現場品質向上」に再投下できます。
- 現場管理アプリ、工事進捗チャット、クラウド型工程表を導入し、現場と事務所の情報共有を徹底
- 見積・書類作成のテンプレート化、コミュニケーションフローの自動リマインド設定
- 定型業務のパートタイム・外部委託化で、正社員は「利益を生む活動」に集中
4. 人材育成と営業ノウハウの共有
営業・現場・事務それぞれのスタッフが「自分の一手が利益改善につながる」と実感する体制作りが、継続した売上高増と利益拡大のコアになります。OJTと定例勉強会を組み合わせ、ナレッジを循環させましょう。
- 営業ロールプレイング研修、案件シミュレーションを定期導入
- 利益改善事例や失敗事例を全社で共有、「なぜ利益が下がったか」「なぜ高利益を実現できたか」の要因分析会を月次開
- 各ポジションごとに業務目的・目標と成果指標を明文化し、評価制度に反映
5. 資金繰りとキャッシュフロー管理の見直し
売上高が増えても、工期遅延や回収サイトの長期化で資金繰りが悪化すれば、利益改善どころか倒産リスクすら高まります。運転資金の状況、資材仕入れ支払いサイト、入金サイトを常時可視化し、経営体力を保つことが最終的な利益強化につながります。
- 毎月のキャッシュフロー予実管理、立替金・未収金の定期チェックと回収フロー見直し
- 取引先別の支払・回収条件の最適化(新規・既存で差をつけるなど)
- 資金繰り悪化時のBCP(事業継続計画)を事前に策定
よくある疑問Q&A
- Q. 利益改善と売上高アップ、どちらを優先すべき?
- A. どちらも大切ですが、赤字受注や薄利多売の売上高増加では意味がありません。まずは「利益率の確保」を最優先し、安定した利益を生む売上高に絞って伸ばすことです。
- Q. 利益改善がうまくいかない原因は?
- A. 原価管理の甘さや、値引き依存、作業工数のむだ、定期的な改善PDCA不在などが典型的な原因です。それぞれを現場レベルで細分化し、具体的見直しを行いましょう。
- Q. 小規模工務店でもできる具体策は?
- A. 顧客管理の徹底、小回りの効く対応力を活かしたリピート営業、原価・業務フローの可視化などは規模を問わず有効です。Excelや安価なクラウドツールも活用できます。
- Q. 営業戦略の見直しタイミングは?
- A. 利益率や売上高の前年比が落ち込んだ時、または新規・既存客構成に偏りが出た時が見直しの好機です。年次・半期ごとに最低一度は現状分析と戦略点検を行いましょう。
利益改善を継続的に成功させるための「次の一手」
最先端のコンサル手法やITシステム導入だけで「利益改善」が達成できると思っていませんか? 本当に重要なのは、「実行」と「継続」の推進力を現場に根付かせるマネジメント力です。このセクションでは、利益改善を再現性高く継続するための応用戦略、効果測定、今後の発展性に至るまで具体的に解説します。
1. 改善PDCAサイクルの全社導入
一度利益改善策を打っただけで終わりにならないために、毎月の「PDCAサイクル」を組織の当たり前にしましょう。特に、現場と経営陣の垣根を超えた「見える化・報告文化」が持続的な売上高と利益成長の起点になります。
- 改善担当者・会議体(営業、現場、会計)の責任分担を明確化
- KPI(利益率UP率・再受注率・原価率・粗利額)の進捗、未達ポイントの要因特定、改善策立案~実行を毎月定例で回す
- 改善成果・失敗事例も含め、ニュースレターや社内掲示板で全員にフィードバック
2. IT・デジタル活用による業務精度アップ
成長力の高い工務店は、積極的にデジタルツールを使いこなしています。利益改善のための仕組みづくりにも、IT活用は有効です。
- 原価計算・案件損益管理ツール、顧客管理(CRM)、工程・現場進捗アプリの導入
- 営業活動や現場対応を「数値化・記録」し、主観や感覚に頼らない経営へシフト
- メール・SNS・Web面談などオンラインチャネルの併用で人的リソース最適化
3. 定期的な外部目線の導入
自社の慣習や思い込みにとらわれず、本当の意味での利益改善につなげるには、年1〜2回で構いませんので「第三者視点(外部コンサル・同業交流会・金融機関審査員)」などを定例で導入しましょう。外部の力を上手に活用し、自社の成長を加速させます。
- 士業やコンサルタントによる現場同行フィードバック
- 同業との相互事例研究会、ベンチマーク
- 助成金・補助金活用や新サービス開発のアドバイスをもらう
4. 社員のエンゲージメント強化
全員が「自分ごと」として利益改善に向き合う雰囲気づくりが、最も強い経営基盤となります。トップダウンだけでなく、現場主導の提案制度、社内表彰制度の運用などで「改善参加型組織」へのシフトを検討しましょう。
- 現場・営業の「改善提案」採用制度、自主チームプロジェクト
- 利益改善達成チーム・個人の社内表彰・インセンティブ
- 新入社員や若手のアイデアプレゼン大会
5. 売上高と利益改善の関係を定期点検し続ける
「今年は売上高が上がったが、利益が思ったほど伸びていない…」この状態のまま放置せず、半年〜1年ごとに「収益構造の見直し」と「戦略の再検証」を行いましょう。これを続けることで、時代や市場変化にも強い会社へ進化できます。
- 定例戦略会議(営業・現場・経理合同)で「数字を軸とした経営意思決定」を習慣化
- 利益指標と売上高推移のグラフ化・傾向分析を定期実施
- 新規事業やサービス多角化への投資リターンも必ず数値評価
まとめ
本記事でご紹介した売上高増加と利益改善の実践ステップは、単なる理論やアイデアではありません。自社の市場分析から商品・価格戦略、案件管理、原価低減、そして社員全員参加型の改善文化まで、どれも「明日から現場で実行できる」具体的なアクションです。これらを一つひとつ導入し、PDCAサイクルを徹底することで、着実に利益体質の強化と持続的な売上高成長を実現できます。小さな一歩でも構いません。継続することで必ず組織は変わり、経営の安定・次代の発展につながります。今日から、できることから始めましょう。皆さまの工務店経営に心からエールを送ります。
工務店の集客・営業ならジーレックスジャパン →ホームページはこちら
商品の差別化へ!制振装置はこちらから →耐震・制振装置
友達申請お待ちしてます! →代表浄法寺のfacebook
工務店のネット集客ならこちら →工務店情報サイト ハウジングバザール
関連記事
-

-
モデルハウスで顧客ニーズを読み解く方法
2025/08/23 |
多くの工務店が直面する大きな課題のひとつは、「お客様の本音や隠れた要望をいかに的確に読み取り、提案や...
-

-
イベントを成功させるための社内体制構築
2025/07/18 |
工務店が地域で存在感を高め、顧客との信頼関係を築きながら持続的な成長につなげるには、イベントの開催が...
-
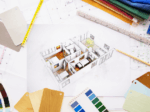
-
失敗しないイベント企画!工務店が押さえるべきポイント
2025/10/24 |
工務店の経営において、集客や地域認知度アップ、顧客との信頼構築は永遠のテーマです。その中で「イベント...
-

-
イベント参加者層を分析!ターゲットに響く企画改善
2025/10/07 | 工務店
工務店経営者の皆様、日々の業務お疲れ様です。地域の皆様に愛される家づくりを目指す中で、集客やブランデ...





























