事業承継税制を活用する!工務店の節税メリット
公開日:
:
工務店 経営
工務店の経営者の多くは「自分の代で終わらせたくない」「大切な技術・ノウハウを次世代にしっかり継承したい」と考えていらっしゃることと思います。しかし、事業承継の過程では高額な相続税・贈与税の負担や、後継者への株式移転によるコスト、さらには名義変更や取引先への配慮など、多くの実務的な障壁に直面します。事業承継税制は、こうした悩みを緩和し、円滑な世代交代を実現する強力な武器となります。本記事では、工務店ならではの事業承継の課題に寄り添いながら、実際の活用アクションをステップごとに解説。さらに、事業承継税制を活用した場合の節税メリットも具体的に明示します。事業承継を「先延ばし」にせず、今着手することで得られる未来への確かな一歩を、ぜひこの記事から掴み取ってください。
事業承継税制の「実践的」導入戦略:基礎から応用まで
工務店の経営にとって事業承継は最重要課題の一つです。ここでは、事業承継の全体像と、事業承継税制の基本をしっかり押さえつつ、効率的に準備を進める具体的なステップを紹介します。
1. 事業承継の「現実」を理解する
工務店のような地域密着型・職人型ビジネスでは、「ノウハウの消失」「後継者不足」「財務面の負担」など、標準的な中小企業以上に困難が生じがちです。現実を正しく把握し、全体を俯瞰することが第一歩となります。
- 後継者候補の有無や意向確認
- 自社株の評価や資産状況の棚卸し
- 経営者個人と会社財産の分離度合いの分析
2. 事業承継税制の概要を押さえる
事業承継税制とは、一定の条件を満たした中小企業が、贈与や相続で非上場株式を後継者へ移転する際、納税を猶予・免除できる制度です。2018年の特例措置(2027年12月末まで認定申請可能)により、適用範囲が格段に広がりました。使いこなすことで、相続税・贈与税負担ゼロでの承継も現実的となります。
- 適用には「認定中小企業」として所轄庁の承認が必要
- 対象は「非上場株式」や出資など
- 後継者1名もしくは複数名体制も認められる場合あり
3. 工務店が押さえるべき「適用要件」と注意点
事業承継税制の活用は「要件クリア」が出発点。特に次のポイントを入念に確認しましょう。
- 業種要件(建設業は原則対象。ただし副業の比率にも注意)
- 雇用の8割維持義務(5年間で平均8割、特例で弾力化あり)
- 事業を10年以上営み、経営に従事してきた承継者
- 贈与・相続時点で代表者が交代していること
4. 準備段階で実行すべきアクション
- 会社・グループの現状分析、承継計画の策定
- 取引金融機関や税理士・行政書士との情報共有
- 後継者育成プラン作成(OJT、外部研修など)
- 株式評価に関わる持株の集約、整理(分散時は買い集め検討)
5. 実践ステップ:導入から認定取得まで(時系列整理)
- 現状分析・事業承継計画の作成
- 都道府県への「特例承認申請書」提出(認定支援機関の確認必要)
- 取締役会・株主総会で後継者としての意思決定・登記
- 贈与や相続発生→税務申告時に「猶予申請」
- 5年間の継続届出・雇用維持義務の管理
6. 導入初期フェーズで頻出する疑問Q&A
- Q1:承継後に業績悪化で雇用が8割維持できなかった場合は?
A1:雇用確保要件は弾力的に運用されているため、きちんとした理由を説明できる場合(災害、業界不振等)は猶予が打ち切られることはありません。 - Q2:実際に納税猶予を受けた後で、途中離職(後継者退任)があった場合は?
A2:退任した時点で猶予された税金の納付猶予が打ち切られることになりますので、退任タイミングや事業計画の見直しが重要です。
事業承継×事業承継税制:成果を最大化する具体的な取り組み
事業承継は準備が整えば完了、というものではありません。ここでは事業承継税制を活用し、「コスト最小・効果最大」の承継戦略を構築するための具体的プロセス・ツール・ケーススタディを紹介します。
1. 実践ステップ【承継期(実行直前・直後)のアクション】
- 経営権・株式の移転スケジュールを具体的に設計
- 移転時期による贈与税or相続税の最適化シミュレーション
- 暦年贈与活用や段階的承継も検討
- 節税メリットを最大限享受するための「特例適用確認」
- 資本金・売上規模・役員構成見直し
- 副業・不動産業などの収益構造精査
- 「経営承継円滑化法」の他制度とも併用
- 遺留分に関する民法特例(後継者へ集中して株式移転が可能)
- 事業用資産の分割・分配ルールの明文化
- 金融機関・主要取引先への経営承継説明
- 与信継続・新代表者の信用維持
- 段階的二代体制移行のコミュニケーション設定
- 株式評価の「適正化」
- 不要資産の除却・役職員持株の整理
- 退職金支給による株式評価低減
2. 工務店の実例で読み解く事業承継・事業承継税制の活用パターン
- 【ケースA】代表取締役会長から長男へ株式100%承継、株評価1億円→贈与税約2000万円→事業承継税制で納税ゼロ
- 【ケースB】複数兄弟体制、長男代表・次男専務に分散承継→議決権集中のため株式一旦集約→特定経営承継期間内に再分配
- 【ケースC】不動産業との兼業、利益の半分が不動産収入→年度ごとに主業従事割合を精査、「建設業」要件クリアで適用
3. 税理士・専門家との連携を成功させるコツ
- 「事業承継専門」「商工会・対応実績豊富」な税理士・行政書士を選任
- 少なくとも2年に一度、制度改正や要件確認で共同見直し
- 強みや課題が異なる場合は複数士業の「チーム」で意見集約
4. 失敗しない「手続き」「運用」上のQ&A
- Q1:5年後に規模が大きくなったら事業承継税制の適用外になりますか?
A1:原則として事業承継時点の要件で判断されるため、途中の規模拡大は直ちに適用外とはなりません。 - Q2:承継後に本業比率が5割未満になった場合はどうなりますか?
A2:実態による精査となりますが、基準年度ベースで継続的に8割維持などの緩和措置があります。
事業承継を継続的に成功させるための「次の一手」
事業承継は一度完了すれば終わりではありません。ここからは持続的な発展を目指すために重要となる「アフターフォロー」と「継続的改善」について詳しく解説します。
1. 承継後の社内コミュニケーションと組織体制見直し
- 新体制スタート時にはキックオフミーティングや個別面談で職人・スタッフの不安払拭
- 経営理念・ビジョン再共有(内部報告会・全体合宿開催も有効)
- 承継後1年以内に組織役割分担や業務プロセス再設計を実施
2. 承継後の業績評価・PDCAサイクルの確立
- 承継前後でのKPI(利益率、リピート率、社員定着率)の定期計測
- 目標未達の場合は事業戦略見直し・後継者育成の再教育
- 社員や顧客アンケートも活用し「承継による社内外の満足度」を指標化
3. 継続的節税策の検証と運用メンテナンス
- 毎年、株式評価・事業用資産の見直しを行う
- 雇用維持義務・報告書提出など税制上の手続きの定期チェック
- 事業承継税制以外の補助金・公的制度も横断的に活用
4. 将来世代への「多段階」事業承継も設計
- 現後継者からその次(例:ご子息/ご息女)へのバトンタッチ準備
- 段階承継、共同経営、グループ化など地域特性に応じた多様な形の計画設計
- 承継計画書を公式文書や議事録に残し透明性を高める
5. 事業承継制度・市場環境の変化への機動的対応
- 国の方針や税制改正(2025年以降の見直し予定)に即した柔軟な戦略転換
- 地域の建設業協会・商工会などのネットワークを活用し情報感度を高める
- 事業承継に関する定期的なセミナー・勉強会の継続受講
6. アフター承継でよくある疑問Q&A
- Q1:承継後に株式の再配分や相続の必要が生じた場合でも、事業承継税制は使えますか?
A1:新たな贈与・相続時に再度制度利用が可能な場合もありますので、状況に応じて適用可否を専門家に確認しましょう。 - Q2:承継計画の修正や制度のアップデートはどの頻度で必要?
A2:毎年の決算や税制改正のタイミングで「定期レビュー」をルーチン化することが望ましいです。
まとめ
工務店における事業承継は、継続的な経営と地域への貢献という大きな役割を担う重要なミッションです。本記事で解説した「事業承継の現実把握」「事業承継税制の活用」「具体的な実践ステップ」「継続的な改善と組織運営」まで、段階ごとに深掘りすることが、スムーズかつ効果的な承継への道となります。今すぐ自社の現状分析から一歩踏み出し、信頼できる専門家や社内の仲間と情報共有しながら、戦略的に事業承継を進めてください。あなたの積極的な準備と実務アクションが、会社も、地域も、家族もより豊かな未来へ導く第一歩になります。焦らず、しかし確実に「持続する工務店経営」のバトンを未来へつないでいきましょう。
工務店の集客・営業ならジーレックスジャパン →ホームページはこちら
商品の差別化へ!制振装置はこちらから →耐震・制振装置
友達申請お待ちしてます! →代表浄法寺のfacebook
工務店のネット集客ならこちら →工務店情報サイト ハウジングバザール
関連記事
-

-
イベント効果を正確に測定する方法と分析のポイント
2025/08/18 |
工務店の経営において、イベントの開催は顧客との信頼構築や新規顧客の獲得、リピーターの創出に直結する重...
-

-
顧客の興味を引くイベントテーマの選び方:工務店のための実践的ガイ
2025/08/21 | 工務店
工務店の経営者の皆様、日々の業務に追われる中で、集客やブランディング、そして何よりも安定的な顧客獲得...
-
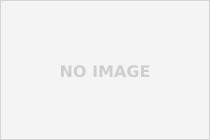
-
工務店の資金繰りを安定させるキャッシュフロー管理術
2025/09/27 |
工務店を経営する中で、資金繰りの悩みは切実な課題となります。「売上はあるが資金が足りない」「支払い...
-
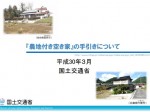
-
工務店 リフォーム 農地つき空き家の手引はコレ
2024/10/22 |
国土交通省は2023年10月4日、農地付き空き家の円滑な活用を促進するための関連制度をまとめた「...





























