子育て卒業後の空き部屋が宝の山に!シニア世代の新たな部屋活用術
公開日: : 家づくりのお役立ち情報
PR:あなたの建築予定地にある工務店に、無料で間取り・見積り作成を依頼してみませんか?お申し込みはこちらから
子どもが巣立った後の空き部屋、どう活用していますか?せっかくのスペースを物置化させるのはもったいない!本記事では、子育てを終えたご家庭の空き部屋を有効活用する方法を詳しくご紹介します。シェアスペースとしての活用から副収入を得る方法、シニア世代の暮らしを豊かにする空間づくりまで、マイホームの新たな可能性を探りましょう。家族構成の変化に合わせた住まいの再設計で、第二の人生をより充実させるヒントが満載です。
目次
・空き部屋問題とは?子どもの独立後に直面する住まいの課題
・活用法その1:シニア世代の趣味と健康を充実させる空間づくり
・活用法その2:収益化からシェアまで、空き部屋の社会的活用術
・活用法その3:将来を見据えた空き部屋リノベーションのポイント
・まとめ:子育て後の住まいを再設計し、豊かなセカンドライフを
空き部屋問題とは?子どもの独立後に直面する住まいの課題
「子どもたちのために」と購入したマイホーム。しかし、子どもが大学進学や就職で家を離れると、突然、使われなくなる部屋が出てきます。国土交通省の調査によれば、子どもの独立後に空き部屋を持つ世帯は全国で約1,200万世帯にも上ると言われています。
「子ども部屋が必要だから」と4LDKの家を購入したものの、気づけば夫婦2人だけの生活。広すぎる家の維持管理に頭を悩ませているご家庭は少なくありません。掃除の手間が増えるだけでなく、冷暖房効率も悪くなりがちです。実際、子どもが独立した後の住宅では、使われていない部屋のために年間約10万円以上の余分な光熱費がかかっているという調査結果もあります。
また、心理的な側面も見逃せません。「子どもの形見」のように残された部屋は、空っぽの巣症候群(エンプティネスト・シンドローム)と呼ばれる心理状態を引き起こすこともあります。子育てに捧げてきた時間とエネルギーの行き場がなくなり、喪失感や孤独感を感じるケースも少なくないのです。
しかし、この「空き部屋問題」は実は大きなチャンスでもあります。子育て期には叶わなかった夢や趣味のための空間、あるいは新たな収入源として活用することで、シニアライフをより豊かにする可能性を秘めているのです。
特に近年は、少子高齢化に伴い「空き家対策」が社会問題化する中、自宅の空き部屋を有効活用する動きが注目されています。2021年の「住宅土地統計調査」によれば、全国の空き家率は13.6%に達しており、これは約848万戸に相当します。こうした背景から、空き部屋を社会資源として活用する取り組みも広がりつつあります。
マイホームを計画する際には、子どもの成長後の住まい方まで見据えた間取り設計が重要です。「将来、子どもが独立したらこの部屋はどう使おう?」といった視点をあらかじめ持っておくことで、長期的に満足度の高い住まいづくりが可能になります。
では、具体的にどのような活用法があるのでしょうか?次のセクションから、空き部屋の活用アイデアを詳しくご紹介していきます。自分らしいシニアライフを送るための空間づくりのヒントがきっと見つかるはずです。

活用法その1:シニア世代の趣味と健康を充実させる空間づくり
子育て期間中は家族のために時間とスペースを割いてきた方も多いでしょう。しかし、子どもの独立は自分自身の時間を取り戻すチャンスでもあります。空き部屋を趣味や健康増進のための専用スペースに変えることで、充実したシニアライフを実現できます。
健康寿命を延ばす自宅トレーニングルーム
厚生労働省の統計によれば、65歳以上の高齢者の約8割が何らかの運動習慣を持ちたいと考えている一方で、実際に継続できているのは3割程度にとどまります。その大きな理由の一つが「場所の確保」です。空き部屋をミニジムに改造することで、天候や時間を気にせず運動を習慣化できます。
具体的な設備としては、有酸素運動のためのルームランナーやエアロバイク、筋力トレーニング用のダンベルセットなどが人気です。最近では、オンラインフィットネスプログラムと連携した鏡型ディスプレイを設置する方も増えており、プロのインストラクターの指導を受けながら自宅で効果的なトレーニングができるようになっています。
床材には衝撃吸収性の高いクッションフロアやコルクタイルを敷くことで、関節への負担を軽減できます。また、壁に姿見を設置すれば、フォームチェックも可能になるでしょう。運動時の換気を考慮して、窓の配置や空気清浄機の設置も検討してみてください。
趣味を極める創作アトリエ
定年退職後に新たな趣味を始める方も多いですが、リビングやダイニングでは道具の出し入れが面倒で続かないことも少なくありません。空き部屋を趣味専用スペースにすることで、作業の効率化と継続性が格段に向上します。
特に人気なのが、絵画、陶芸、木工、裁縫などの創作活動です。日本生産性本部の調査では、定年後に趣味を持つ方は持たない方と比較して、生活満足度が20%以上高いという結果も出ています。
アトリエ作りのポイントは、適切な作業台と収納スペースの確保です。たとえば、絵画なら北向きの窓から入る安定した自然光が理想的で、イーゼルや画材棚を効率的に配置できるレイアウトを考えましょう。陶芸なら、土や釉薬の保管場所、成型台、乾燥棚などが必要になります。
また、創作活動は集中力を高めることで認知症予防にも効果があるとされています。国立長寿医療研究センターの研究によれば、週3回以上創作活動に取り組む高齢者は、そうでない方と比べて認知機能低下のリスクが約40%低減するという結果が出ています。
癒しの読書空間と家庭図書館
活字離れが叫ばれる現代ですが、シニア世代の読書時間は他の年代と比較して長い傾向にあります。文化庁の「国語に関する世論調査」によれば、60代以上の1日あたりの平均読書時間は約49分で、全年代平均の約32分を大きく上回っています。
空き部屋を落ち着いた読書空間にリノベーションすれば、集中して読書を楽しめるだけでなく、長年集めてきた蔵書を美しく収納・展示することも可能になります。壁一面の本棚と、快適な読書チェア、適切な照明を備えた読書空間は、多くの書籍愛好家の憧れでしょう。
照明計画は特に重要で、目への負担を軽減する間接照明や調光機能付きの読書灯の設置がおすすめです。また、断熱性・遮音性の高い窓に交換することで、外部の騒音を遮断し、より没入感のある読書体験が可能になります。
最近では電子書籍の普及も進み、タブレット端末で読書を楽しむ方も増えています。充電ステーションを兼ねたサイドテーブルや、Wi-Fi環境の整備も検討してみてください。
このように、空き部屋を自分の趣味や健康のための専用スペースに変えることで、退職後の生活の質を大きく向上させることができます。次のセクションでは、空き部屋を活用して収入を得たり、社会とのつながりを持ったりする方法について見ていきましょう。
活用法その2:収益化からシェアまで、空き部屋の社会的活用術
空き部屋は単なる余剰スペースではなく、社会とつながる窓口や収入源にもなり得ます。シニア世代の経済的自立や社会参加を促進する空き部屋活用法をご紹介します。
副収入を生み出す民泊・ホームシェア
観光庁の統計によれば、2019年の民泊利用者数は約1,100万人に達し、コロナ禍による一時的な落ち込みを経て、再び増加傾向にあります。特に、地方都市や観光地では宿泊施設が不足しがちなため、住宅の一部を活用した民泊サービスの需要が高まっています。
住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行により、年間提供日数が180日以内の場合、一定の条件を満たせば個人でも民泊サービスを提供できるようになりました。実際に取り組んでいる60代の方の事例では、月に10日程度の稼働で平均5〜8万円の収入を得ているケースも珍しくありません。
ただし、民泊は全ての自治体で無条件に認められているわけではないため、地域の条例を確認することが重要です。また、セキュリティ面での懸念から、完全に独立した出入り口を設けたり、専用のキーボックスを設置したりするなどの工夫も必要になります。
民泊ほど手間をかけたくない場合は、長期滞在者向けのシェアハウスの一室として貸し出す方法もあります。特に大学や企業が近い地域では、学生や単身赴任者からの需要が見込めます。月額3〜6万円程度の家賃収入が期待でき、管理会社を介することで、入居者とのトラブル回避や適切な入居審査も可能です。
地域コミュニティの拠点としての活用
少子高齢化が進む日本では、地域コミュニティの希薄化が社会問題となっています。総務省の調査では、65歳以上の高齢者の約15%が「話し相手がいない」と回答しており、社会的孤立が深刻化しています。
そんな中、自宅の空き部屋を地域の交流スペースとして開放する「住み開き」の取り組みが注目されています。週に1〜2回、地域の子どもたちの学習支援や高齢者のサロン、趣味のサークル活動の場として提供することで、新たな人間関係の構築や社会参加の機会が生まれます。
実際に、東京都世田谷区では「地域共生のいえ」として、このような取り組みを行う住宅を認定・支援する制度があり、現在50軒以上が登録されています。活動内容は多岐にわたり、子育て世代の交流会、英会話サロン、料理教室、手芸教室などが開催されています。
このような活動は必ずしも収益目的ではありませんが、適正な参加費を設定することで、光熱費や軽食代程度はカバーできるケースが多いようです。何より、地域に貢献しながら自身の生きがいにもつながる点が大きな魅力といえるでしょう。
テレワーク対応のシェアオフィス化
コロナ禍を機に普及したテレワークは、アフターコロナの時代にも定着しつつあります。総務省の「通信利用動向調査」によれば、テレワーク実施企業の割合は2019年の20.2%から2022年には47.5%へと大幅に増加しています。
こうした社会変化を背景に、住宅の一部をシェアオフィスとして提供するケースも増えています。特に、駅から徒歩圏内の住宅では、周辺のフリーランスや小規模事業者からの需要が見込めます。
設備面では、高速インターネット回線、複合機、ミーティングスペースなどの基本的なオフィス機能を整えることが重要です。また、防音対策や独立した出入り口の確保も利用者からの評価ポイントとなります。
利用料金は立地や設備によって異なりますが、1日単位で1,000〜3,000円、月額会員制にして2〜5万円程度で提供しているケースが多いようです。東京都内では、「下北沢オープンオフィス」のように、一般住宅の1階をコワーキングスペースに改装した好事例も見られます。
以上のように、空き部屋を社会的に活用することで、経済的なメリットだけでなく、新たな人間関係の構築や社会貢献の機会も得られます。次のセクションでは、長期的な視点から空き部屋をリノベーションする際のポイントについて解説します。
活用法その3:将来を見据えた空き部屋リノベーションのポイント
子どもの独立を機に空き部屋のリノベーションを検討する際は、単に現在の用途だけでなく、将来の生活変化も見据えた計画が重要です。このセクションでは、長期的な視点からの空き部屋リノベーションのポイントを解説します。
可変性を持たせた間取り設計
空き部屋の活用法は、家族の状況や社会環境の変化によって変わる可能性があります。そのため、固定的な造作を極力避け、将来的な用途変更に対応できる柔軟な設計が望ましいでしょう。
具体的には、可動式の間仕切りや収納家具を活用することで、同じ空間を異なる用途に合わせて容易に変更できるようになります。例えば、現在は趣味部屋として使用していても、将来的に介護が必要になった場合には寝室や介護スペースに転用できるといった具合です。
建築設計の専門家によれば、リノベーションの際は床や壁の基本構造はシンプルに保ち、用途に応じて家具やカーテンなどの可動要素で空間を区切る「スケルトン・インフィル」の考え方が有効とされています。これにより、将来的な改修コストを抑えることができます。
高齢期を見据えた住環境整備
子どもの独立期は、自身の高齢期も視野に入れたリノベーションのタイミングでもあります。日本建築学会の調査によれば、バリアフリー改修を行った住宅では、居住者の転倒事故が約40%減少するという結果が出ています。将来の身体機能低下を見据えた空間設計を行うことで、住み慣れた家で長く安心して暮らし続けることが可能になります。
具体的な対策としては、段差の解消、手すりの設置、滑りにくい床材の選択などが基本です。特に浴室・トイレ・寝室といった日常生活の重要空間を集約し、動線を短くする工夫も効果的です。空き部屋を1階に移動することで将来的な階段の上り下りを減らせる場合は、思い切って1階に主寝室を移すことも検討価値があります。
さらに、IoT技術を活用したスマートホーム化も注目されています。センサーによる見守りシステムや音声操作による家電制御など、高齢になっても快適に暮らせる技術が急速に進化しています。これらを空き部屋のリノベーションに取り入れることで、将来的な安心感も高まるでしょう。
環境と家計に優しいエコリノベーション
空き部屋のリノベーションは、住宅全体の省エネ性能を高める絶好の機会でもあります。経済産業省の調査によれば、断熱リノベーションを行った住宅では、冷暖房費が平均して20〜30%削減されるというデータがあります。
特に注目したいのが、空き部屋の断熱強化です。壁や天井の断熱材を充填する、窓を二重サッシや Low-E ガラスに交換するといった対策により、部屋の温熱環境が大きく改善します。これは光熱費の削減だけでなく、ヒートショック予防など健康面でも大きなメリットがあります。
また、太陽光発電システムの設置も検討価値があります。FIT(固定価格買取制度)の買取期間が終了する住宅も増える中、自家消費型の太陽光発電と蓄電池の組み合わせが注目されています。特に日中は不在がちなシニア世帯では、空き部屋の屋根や南向きの壁面を活用した発電システムが効果的です。
このように、空き部屋のリノベーションは、単に見た目や機能を更新するだけでなく、住宅の資産価値向上や将来的な維持費削減にもつながる重要な投資と言えるでしょう。専門家のアドバイスを受けながら、長期的視点でのリノベーション計画を立てることをおすすめします。

まとめ:子育て後の住まいを再設計し、豊かなセカンドライフを
子どもの独立は、多くの親にとって一つの区切りであると同時に、新たな人生のスタートでもあります。これまで見てきたように、空き部屋の有効活用は、シニア世代の暮らしを豊かにするための重要な鍵となります。
本記事で紹介した空き部屋活用のポイントをおさらいしましょう:
- 自分自身のための空間づくり:趣味や健康維持のための専用スペースを確保することで、充実したシニアライフを実現できます。
- 社会とのつながりを生み出す活用法:民泊やシェアスペースとして開放することで、新たな人間関係の構築や収入源の確保が可能になります。
- 将来を見据えたリノベーション:可変性を持たせた設計や高齢期の住環境整備、エコリノベーションなど、長期的視点での改修が重要です。
忘れてはならないのは、住まいは常に変化するものだということです。子育て期には子ども中心の間取りが適していても、子どもの独立後は夫婦の暮らしやすさを優先した住まいへと再設計することが大切です。
また、将来の売却や賃貸の可能性も視野に入れておくと、より選択肢が広がります。国土交通省の調査によれば、子どもが独立した後に住み替えを検討する世帯は約25%に上るというデータもあります。必ずしも今の家に住み続ける必要はなく、ライフスタイルの変化に合わせて住まいを選び直す柔軟性も重要でしょう。
最後に、空き部屋の有効活用は一朝一夕には実現できません。専門家のアドバイスを受けながら、自分たちのライフスタイルや価値観に合った活用法を、時間をかけて見つけていくことをおすすめします。全国各地に「空き家活用アドバイザー」や「住まいのコンシェルジュ」といった相談窓口も増えていますので、積極的に活用してみてください。
子どもが巣立った後の空間を、新たな可能性に満ちた「宝の山」に変えることで、第二の人生がより豊かなものになることを願っています。
ハウジングバザール運営アカウントです。
関連記事
-

-
老後も安心!光熱費・固定費を抑える省エネ住宅の選び方と対策
2025/05/09 |
老後の生活費を考えると、光熱費や固定費の負担は大きな不安要素になります。年金生活になってからの家計...
-
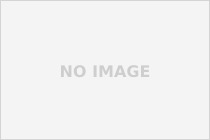
-
長崎県で快適な暮らしを―広々とした4LDK物件で駅チカ生活を満喫
2023/10/03 |
イントロダクション 長崎県は、歴史的な名所や美しい自然環境が誇る、日本の魅力的なエリアの...
-

-
土地探しの成功法則:初心者が知っておくべきコツとポイント
2025/01/18 |
土地探しは、マイホーム計画において最も重要なステップの一つです。特に、43歳の初心者ママであるあな...
-

-
子育て世代でも考えたい!老後も安心快適な住まいづくりのポイント
2025/05/08 |
年齢を重ねても安心して暮らせる家づくりは、実は子育て世代の今から考えるべき大切なテーマです。住宅ロ...














