新築で後悔しない!家の「収納力」を最大限に引き出す設計術
公開日: : 最終更新日:2025/08/30 家づくりのお役立ち情報
マイホームの夢を育む中で、間取りやデザインと同じくらい大切なのが「収納」のこと。特に、お子さんの成長とともに増えるモノ、季節ごとの家電や衣類、趣味の道具など、「家を建てたらモノがあふれて片付かない…」なんて後悔はしたくないですよね。家族みんなが快適に、そして心地よく暮らすためには、設計段階から「収納力」を意識することが何よりも重要です。このガイドでは、あなたの理想の暮らしを叶えるため、新築住宅の収納計画で押さえるべきポイントを徹底解説します。家族構成やライフスタイルの変化を見据えながら、家の「収納力」を「最大限に引き出す」ための具体的なヒントを、一緒に見ていきましょう。
目次
- 新築計画で「収納力」を最大限に引き出すための基礎知識
- 家族の成長とモノに合わせて「収納力」を劇的にアップさせる間取り術
- 将来後悔しない!「収納力」を維持・発展させる長期的な視点とアイデア
- まとめ:理想の暮らしは「収納」から
新築計画で「収納力」を最大限に引き出すための基礎知識
新築の家づくりを始める際、多くのご家族が真っ先に考えるのは、LDKの広さやデザイン、水回りの設備などかもしれません。しかし、実際に住み始めてから「もっと収納があればよかった」「モノが収まらない」と後悔する声は少なくありません。そうならないためにも、まずは家の「収納力」を「最大限に引き出す」ための基本的な考え方をしっかりと押さえておくことが大切です。
なぜ新築時に収納計画が重要なのか
収納は、単にモノをしまう場所ではありません。家の快適さ、片付きやすさ、さらには家族の心のゆとりにも直結する非常に重要な要素です。一度家を建ててしまうと、後から大がかりな収納を追加するのは費用も労力もかかります。例えば、壁一面の造作収納やウォークインクローゼット、広いパントリーなどは、設計段階で組み込まなければ実現が難しいでしょう。新築時にしっかりと計画することで、住んでからの「収納がない」という不満を解消し、常に整理整頓された美しい住まいを維持することができます。また、ご夫婦と小学生のお子様お二人というご家族構成の場合、お子様の成長に伴って、おもちゃ、学用品、部活動の道具、教科書、思い出の品など、驚くほどモノが増えていきます。これらをどこにどう収めるかを先回りして考えることが、未来の家族の快適な暮らしを守る第一歩となるのです。
「収納力」の基本的な考え方と種類
「収納力」と一言で言っても、その種類や機能は多岐にわたります。まずは、代表的な収納の種類とその特徴を理解しましょう。
- 造作収納(作り付け収納):壁の一部として設計段階から組み込まれる収納です。特定の場所にぴったりと収まるため、空間の有効活用に優れています。例えば、リビングのテレビボードと一体になった収納、キッチンカウンターの下の収納、階段下のデッドスペースを活用した収納などが考えられます。オーダーメイドで家族のライフスタイルに合わせた最適な形で作れるため、まさに「収納力」を「最大限に引き出す」切り札となるでしょう。
- ウォークインクローゼット(WIC):人が中に入ってモノを選べるほどの広さを持つ収納空間です。衣類だけでなく、バッグ、小物、オフシーズンの家電などもまとめて収納でき、非常に高い「収納力」を誇ります。寝室に設けることが多いですが、玄関近くに家族全員で使えるファミリークローゼットとして設けることで、各部屋に大きな収納を設けずに済むメリットもあります。
- パントリー(食品庫):キッチン周りの食料品や日用品、災害備蓄品などをストックする専用の収納です。常温保存できる食材や飲料、普段使いしない大型の調理器具などをまとめて収納できるため、キッチン全体をすっきりと保ち、「収納力」を高める上で非常に有効です。勝手口の近くに設けることで、買い物帰りの収納もスムーズになります。また、家族4人分の食料品や日用品をストックするためには、最低でも1畳以上のスペースを確保するのが理想的だと言われています。
- 可動棚・オープン棚:棚板の位置を自由に変えられるタイプや、扉のないオープンな収納です。可動棚であれば、お子様の成長や収納するモノの大きさに合わせてフレキシブルに対応できます。オープン棚は、見せる収納として機能することもあれば、頻繁に使うモノをサッと取り出せる利便性も持ち合わせています。ただし、オープンな分、常に整理整頓を心がける必要があります。
- 外部収納・小屋裏収納:アウトドア用品、タイヤ、工具など、家の中にはあまり置きたくないモノを収納するスペースです。ガレージや玄関脇の外部収納、屋根裏を利用した小屋裏収納などは、家全体の「収納力」を底上げし、「最大限に引き出す」上で非常に有効です。特に季節物や使用頻度の低い大型のものを収納するのに適しています。小屋裏収納は固定階段を設けることで、安全性と利便性が格段に向上します。
現在の持ち物を把握し、必要な収納量を割り出す
闇雲に収納を増やしても、本当に必要な「収納力」を確保したことにはなりません。まずは、現在お住まいの家にあるモノを全て把握し、今後新居に持ち込むモノの量を具体的にイメージすることが重要です。
おすすめは「断捨離」と「見える化」です。
- 断捨離:新居への引越しは、モノを見直す絶好のチャンスです。「いつか使うかも」「もったいない」という気持ちを手放し、本当に必要なモノ、大切なモノだけを見極めましょう。家族みんなで取り組むことで、それぞれの持ち物を意識するきっかけにもなります。
- 見える化:現在の収納スペースの状態を写真に撮ったり、実際にメジャーで計測したりして、現時点での収納量と収納しているモノの量を把握します。例えば、衣類はどのくらいの量があるか(丈の長いもの、畳むものなど)、書籍はどのくらいか、お子様のおもちゃは現在どのくらいあるか、今後増える可能性があるか、などを具体的にリストアップします。これにより、漠然とした「収納が足りない」という感覚が、具体的な「ここにこれくらいの広さの収納が必要」という要望に変わります。
一般的に、家の延床面積の10%~15%程度が収納スペースとして確保されていると、快適に暮らせると言われています。例えば、延床面積が30坪(約100㎡)の家であれば、収納スペースは最低でも3坪(約10㎡)は欲しいところです。しかし、これはあくまで目安です。ご家族のライフスタイルや所有物の量によって、最適な「収納力」は大きく異なります。しっかりと持ち物を把握し、それに見合った収納計画を立てることが、「収納力」を「最大限に引き出す」ための第一歩となります。

家族の成長とモノに合わせて「収納力」を劇的にアップさせる間取り術
理想の「収納力」は、単に広さだけでは決まりません。どこに、どんな種類の収納を、どれくらいの量で配置するかという「間取り」が、その家の「収納力」を「最大限に引き出す」鍵を握ります。ここでは、家族のライフスタイルの変化を見据えながら、各場所で効果を発揮する収納の間取り術をご紹介します。
場所別!適材適所の「活用収納」設計
「使う場所に、使うモノをしまう」という原則に立ち返り、それぞれの場所でどのような収納が必要か具体的に考えていきましょう。
- 玄関:家族もゲストもスッキリ「魅せる+隠す」収納玄関は、家族が毎日通るだけでなく、来客の際に一番最初に目にする場所です。靴だけでなく、ベビーカー、傘、外遊びのおもちゃ、アウトドア用品、防災リュックなど、意外とモノが多くなりがちです。
「収納力」を「最大限に引き出す」には、まず靴の収納量を多めに確保することが重要です。家族それぞれの靴の量だけでなく、来客用のスリッパや、お子さんの成長によって増える可能性のある運動靴なども考慮しましょう。可動棚式の収納は、ブーツや長靴など高さのある靴の収納にも対応でき便利です。
加えて、コートクロークや土間収納(シューズクローク)を設けるのが非常に効果的です。特に土間収納は、汚れたものをそのまま置けるため、お子さんの部活動用品やベビーカー、ゴルフバッグなど、家の中に持ち込みたくないモノを収納するのに最適です。扉を設けることで、急な来客時でも生活感を隠し、スッキリとした玄関を保つことができます。 - LDK(リビング・ダイニング・キッチン):家族の司令塔としての「多機能収納」LDKは家族が集まる中心のスペースであり、最もモノが集まりやすい場所です。リビングには家族共用の文具、薬、書類、ゲームなど、ダイニングには配膳用品、キッチンには食器や調理器具、食品ストックが必要です。
キッチンでは、パントリーは必須とも言えるでしょう。背面収納(カップボード)は食器だけでなく、ホットプレートやホームベーカリー、ミキサーなどの調理家電を収納できるタイプを選び、コンセントの位置も検討しましょう。引き出し収納は奥まで見渡しやすく、フライパンや鍋の収納に適しています。
リビングダイニングでは、散らかりがちなモノを「一ヶ所に集約」できるような共有収納を設けるのがおすすめです。例えば、壁面収納やテレビボードと一体になった造作収納は、見た目も美しく「収納力」も高いです。扉を閉めれば、急な来客時でも簡単に片付いた印象を与えられます。お子さんの学用品やランドセル置き場を、リビングの一角に専用スペースとして設けることで、リビング学習の習慣化にも繋がり、散らかり防止にもなります。 - 子供部屋:成長に寄り添う「可変性収納」小学生のお子様がいるご家庭にとって、子供部屋の収納は特に悩ましいポイントです。入学前のおもちゃや絵本が主な収納対象だったのが、小学生になると教科書、参考書、学用品、習い事の道具、そして服と、モノが多様化し、量も増えていきます。さらに中学生、高校生と成長するにつれて、趣味のモノや思い出の品も増え、ライフスタイルも変化します。
そこで重要なのが「可変性」のある収納です。造り付けの大きなクローゼットだけでなく、高さを変えられる可動棚を多く採用しましょう。最初は絵本やおもちゃを低めに収納し、成長とともに教科書や参考書、私服を収納できるよう、棚板のピッチを細かく設定できるタイプが理想的です。
また、将来的に個室を分ける可能性も考慮し、共有スペースとして使える空間に十分な収納を設けることも一案です。例えば、それぞれの個室には最低限の収納(例えば幅1m程度のクローゼット)のみを設け、廊下や共有スペースに家族で使える大きなファミリークローゼットや納戸を設けることで、各部屋の圧迫感を減らし、子供部屋をより有効に活用できます。 - 寝室:ゆとりを生む「見せる収納と隠す収納」夫婦の寝室は、リラックスできる空間であることが第一です。そのため、衣類や寝具、趣味のモノなどをスッキリと収納できる工夫が求められます。
ウォークインクローゼット(WIC)は、やはり寝室の「収納力」を「最大限に引き出す」最適な方法です。衣類だけでなく、着替えの際に必要な小物やアクセサリー、オフシーズンの寝具、キャリーケースなどもまとめて収納できます。広さに余裕があれば、アイロン掛けや身支度ができるスペースを設けるのも良いでしょう。
ウォークスルー型のWICにすれば、洗濯動線とつながり、家事効率もアップします。また、WICまでもない場合は、壁面収納や深めのクローゼットを設置し、収納ケースなどを活用して縦方向の空間を有効活用しましょう。見せる収納としては、お気に入りの雑貨や本を飾れるようなニッチや棚を設けるのも、空間のアクセントになります。 - 水回り・その他:デッドスペースも活用「隙間収納」洗面所やトイレ、お風呂といった水回りは、限られたスペースながら、タオルや洗剤、ストック品など、細々としたモノが多く集まる場所です。
洗面所には、リネン庫や洗剤のストックを収納できる稼働棚式の収納を設けるなど、縦方向の空間を有効活用しましょう。タオルやパジャマ、下着なども収納できると、入浴時の動線がスムーズになります。
トイレの背面や上部にニッチや吊り戸棚を設けることで、トイレットペーパーのストックや掃除用具などをスッキリと収納できます。
また、家全体を見渡すと、階段下、廊下、小屋裏、屋根裏、床下など、意外な場所にデッドスペースが隠されています。これらを積極的に収納スペースとして活用する(「収納力」を「最大限に引き出す」)ことで、本来の居住空間を圧迫することなく、収納量を増やすことができます。例えば、階段下は奥行きのある収納として掃除用具や季節家電の収納に、小屋裏や床下は、湿度管理に注意しながら季節物や防災用品の収納に活用できます。
家族みんなが使いやすい収納の工夫
優れた「収納力」は、単にモノが収まるだけでなく、家族全員が「使いやすい」と感じることで初めてその真価を発揮します。
- 家族一人ひとりの収納場所:共有スペースに家族全員のモノをまとめてしまうのではなく、それぞれの持ち主が管理しやすいパーソナルな収納場所を設けることも大切です。例えば、子供部屋だけでなく、リビングに各自の「お道具箱」のような場所を作ることで、片付け習慣を自然に身につけさせることができます。
- 取り出しやすさ・しまいやすさ:頻繁に使うモノは、かがまずに手の届くゴールデンゾーン(目線の高さから腰の高さまで)に収納しましょう。重いモノやあまり使わないモノは、下段や上段に。奥行きがありすぎる収納は、奥のモノがデッドスペースになりがちなので、手前に引き出せる収納ユニットや、キャスター付きの収納ケースなどを活用すると良いでしょう。
- 収納物のラベリング:特にパントリーや納戸など、中身が見えにくい収納には、ラベリング(表示)をすることで、家族誰もがどこに何があるかすぐにわかるようになり、片付けの手間を減らすことができます。
これらの設計術と工夫を取り入れることで、あなたの新居は、ただ広いだけでなく、家族みんなが快適に、そして心地よく暮らせる「収納力の高い家」となるでしょう。

将来後悔しない!「収納力」を維持・発展させる長期的な視点とアイデア
新築で十分な「収納力」を確保したとしても、それだけで安心とは限りません。家族構成の変化、お子さんの成長、ライフスタイルの変化、そして趣味や嗜好の移り変わりによって、必要な「収納力」や収納物の種類は常に変化していきます。せっかく「最大限に引き出す」設計にした収納を、将来にわたって賢く使い続けるための長期的な視点とアイデアをご紹介します。
ライフステージ変化に対応する「フレキシブル収納」
家は一度建てたら終わりではありません。住み続ける限り、私たちの暮らしは変化し続けます。特に、この先の数十年を見据えた時に、お子さんが巣立った後、夫婦二人になった時の暮らし、さらには介護が必要になった時の暮らしなど、様々なシナリオを想定しておくことが大切です。
- 子供部屋の可変性:お子さんが独立した後、子供部屋はどう使われるでしょうか。予備の寝室、書斎、趣味の部屋、または大きな収納スペースとして活用することも考えられます。子供部屋のクローゼットや棚は、子供が巣立った後に夫婦の衣類や思い出の品などを収納できるような、汎用性の高いデザインにしておくと良いでしょう。例えば、あらかじめ壁に棚柱用の下地を入れておけば、後から棚板を追加したり、デスクを取り付けたりするのも容易になります。
- 多目的スペースの確保:特定の用途を決めすぎず、フレキシブルに使える多目的スペースを設けることも、「収納力」を「最大限に引き出す」上で有効です。例えば、廊下の一角に奥行きの浅い共有の本棚を設ける、リビングの一角に勉強や作業ができるカウンターと収納を設けるなどです。子供が小さいうちは遊び場として、成長したら学習スペースとして、将来的には夫婦の書斎や趣味のスペースとして、家具の配置や収納の中身を変えるだけで、空間を柔軟に活用できます。
- 季節物・イベント用品の長期保管:雛人形や五月人形、クリスマスツリー、季節ごとのイベント用品、スキー・スノーボード用品など、使用頻度は低いけれど場所を取るモノは意外と多いものです。これらをまとめて収納できる場所、例えば小屋裏収納や外部収納、トランクルームの活用なども視野に入れると、普段の生活空間を圧迫することなく、「収納力」を確保できます。
維持管理のしやすさも「収納力」の一部
せっかく多くの収納スペースを設けても、使い勝手が悪かったり、管理がしにくかったりすると、結局モノがあふれてしまいます。
- 掃除のしやすさ:収納内部の素材選びも重要です。ホコリが溜まりにくく、拭き掃除がしやすい素材を選ぶことで、常に清潔な状態を保ちやすくなります。また、キャスター付きの収納ボックスを活用すれば、重いものでも楽に移動させて掃除ができます。
- 換気と採光:特にウォークインクローゼットやパントリー、納戸などは、湿気がこもりやすい場所です。カビや虫の発生を防ぐためにも、窓や換気扇を設けて空気の入れ替えができるようにすることが大切です。また、照明を適切に配置することで、奥まで見やすく、モノの出し入れがスムーズになります。
デジタル化とモノの循環を考える
現代社会において、モノの「収納力」を考える上で、デジタル化の視点も欠かせません。
- 書類のデジタル化:学校の書類、家電製品の取扱説明書、保証書、写真など、紙媒体の書類は増え続ける一方です。これらをスキャンしてデータ化することで、物理的な収納スペースを大幅に節約できます。重要書類もクラウドストレージにバックアップを取っておけば、いざという時の安心にも繋がります。
- モノの「出口」を意識する:新しいモノが入ってくる一方で、使わなくなったモノは適切に手放す習慣を身につけることが、「収納力」を維持する上で最も重要です。「使わないモノを溜め込まない」という意識を家族全員で共有しましょう。フリマアプリの活用、リサイクルショップへの持ち込み、地域の資源回収など、モノの「出口」を意識することで、収納がモノであふれるのを防ぎます。
- 「借りる」という選択肢:使用頻度が非常に低いけれど、いざという時に必要になるモノ(例えば、高圧洗浄機や脚立、パーティー用品など)は、購入せずにレンタルサービスを利用することも賢い選択です。これにより、自宅の「収納力」を他の必要なモノのために「最大限に引き出す」ことができます。
これらの長期的な視点を持つことで、新築時に確保した「収納力」を将来にわたって「最大限に引き出す」ことが可能になります。家づくりはゴールではなく、日々の暮らしをより豊かにするためのスタートラインです。計画段階からこれらの点を考慮することで、ずっと快適な住まいを実現できるでしょう。
まとめ:理想の暮らしは「収納」から
マイホーム計画において、家の「収納力」を「最大限に引き出す」ことは、単にモノを片付けるという行為を超え、ご家族みんなの心にゆとりと快適さをもたらす重要な要素であることがお分かりいただけたでしょうか。30代から50代で小学生のお子さんがいるご家庭では、日々増えていくモノと、成長する家族のライフスタイルの変化に対応できる柔軟な収納計画が特に求められます。
今回の記事でご紹介したように、まずは現在の持ち物を把握し、ご家族にとって本当に必要な収納量を割り出すことから始めましょう。そして、玄関からLDK、子供部屋、寝室、水回り、さらにはデッドスペースに至るまで、各場所の特性と家族の行動動線を踏まえた「適材適所」の収納計画を立てることが重要です。造作収納やウォークインクローゼット、パントリー、可動棚、外部収納などをバランス良く組み合わせることで、空間を有効活用し、まさに「収納力」を「最大限に引き出す」ことができます。
また、家は長く住む場所です。お子様の独立や家族構成の変化を見据え、フレキシブルに対応できる収納、そしてモノのデジタル化や循環といった長期的な視点を持つことで、将来にわたって「いつも片付いている快適な家」を維持できるでしょう。
「収納」は、家の広さや予算の問題だけでなく、いかに賢く、そして将来を見据えて計画できるかにかかっています。ぜひ、このガイドを参考に、ご家族の理想の暮らしを実現するための「収納」計画を始めてみてください。きっと、住み始めてからも「この家にしてよかった!」と心から思える、豊かな毎日が待っているはずです。
関連記事
-

-
山陽小野田市で注文住宅を建てる完全ガイド:相場・費用・間取りを徹
2025/03/15 |
子育て世代の皆さん、マイホームの夢を叶える時が来ましたね。山陽小野田市で注文住宅を建てるなら、知っ...
-

-
窓の位置で後悔しない!失敗談から学ぶ家づくりと理想の窓プラン
2025/09/20 |
マイホーム計画を進めているご夫婦、特に子育て世代の皆さんは、「理想の家」を思い描く一方で、「失敗し...
-
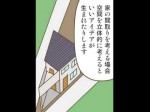
-
変形地・狭小地が得意!変形地・狭小地のメリット・デメリット
2020/03/07 |
変形地・狭小地での家づくりをお考えの皆さんへ、変形地・狭小地で家をつくる際のメリット・デメリットと失...
-

-
シニア世代の住宅ローンを考える:年金だけでも返済可能な方法と不安
2025/10/23 |
老後の生活費と住宅ローンの両立に悩んでいませんか?子育て世代のあなたが将来のマイホーム計画を考える...











