中古住宅の固定資産税まるわかり!築年数やリフォームで変わる税額を徹底解説
公開日: : 家づくりのお役立ち情報
「マイホーム購入」という、人生の一大イベント。お子さんの成長を考えた広い家、憧れの庭付き一戸建て…夢は膨らむ一方で、住宅ローンや維持費など、お金の心配も尽きませんよね。特に、中古住宅を検討されている方にとって、毎年の「固定資産税」は避けて通れない大きな疑問点ではないでしょうか。「築年数によって税金は変わる?」「リフォームしたら高くなるって本当?」といった不安を感じる方も多いかもしれません。
ご安心ください。このブログ記事では、マイホーム計画を始めたばかりのあなたに向けて、中古住宅の固定資産税について、基礎の基礎から分かりやすく解説します。築年数やリフォームが税額にどう影響するのか、そして賢く税金を抑えるためのポイントまで、具体的な計算例を交えながら徹底的にご紹介。これを読めば、中古住宅の固定資産税に関する疑問が解消され、安心してマイホーム計画を進められるようになるはずです。さあ、一緒に固定資産税の謎を解き明かしていきましょう。
目次
- 中古住宅の固定資産税の基本を知ろう
- 築年数・リフォームが固定資産税に与える影響
- 中古住宅の固定資産税を賢く抑えるポイント
- 結論・まとめ
中古住宅の固定資産税の基本を知ろう
中古住宅の購入を検討する上で、毎年のランニングコストとして必ず発生するのが固定資産税です。この税金が一体どのようなもので、どのように計算されるのか、まずはその基本をしっかりと理解しましょう。マイホーム計画を進める上で、資金計画の重要な要素となります。
固定資産税とは?
固定資産税とは、土地や建物、償却資産などの「固定資産」を所有している人が、その所在地の市町村(東京23区内は都)に納める地方税です。毎年1月1日時点の所有者に対して課税され、土地、家屋(建物)、そして事業用の機械装置などの償却資産がその対象となります。中古住宅を購入した場合、あなたはこの固定資産である家屋と土地の所有者として、固定資産税を納める義務が生じることになります。
納税通知書は、通常、毎年4月から6月頃に自治体から送付され、通常は年4回に分けて納付します。初年度は引き渡し日以降の税金を日割りで前の所有者に支払うケースが多いですが、これは売買契約によって異なるため、契約時にしっかりと確認することが大切です。
課税標準額(固定資産評価額)とは?
固定資産税の計算の基礎となるのが、「課税標準額」です。これは、固定資産の価値を自治体が評価して決定するもので、「固定資産評価額」とも呼ばれます。この評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて決定され、3年に一度見直しが行われます。
家屋の評価額は、同じものを再び新築した場合にかかる費用(再建築費)を基準に、築年数による劣化などを考慮して算出されます。つまり、新築時の価格ではなく、あくまで自治体が定めた評価基準に基づいている点がポイントです。土地の評価額は、道路や公共施設への近接性、形状、地価公示価格などを参考に決定されます。この固定資産評価額は、中古住宅の売買価格とは異なる場合がほとんどですので、注意が必要です。
税率と計算方法
固定資産税の税率は、多くの市町村で標準税率である1.4%が適用されています。ただし、自治体によっては、財政状況などによりこれとは異なる税率を定めている場合もありますので、購入を検討している地域の税率を確認しておくと安心です。
固定資産税の計算式は非常にシンプルです。
固定資産税 = 課税標準額 × 税率(標準1.4%)
この課税標準額は、土地と家屋それぞれに算出されます。つまり、土地と家屋の固定資産税を別々に計算し、その合計額があなたが支払う固定資産税となるのです。
具体的な計算例
例えば、あなたが購入を検討している中古住宅の評価額が以下のようだったと仮定しましょう。
- 土地の評価額:1,500万円
- 家屋の評価額:500万円
標準税率1.4%で計算すると、
- 土地の固定資産税:1,500万円 × 1.4% = 21万円
- 家屋の固定資産税:500万円 × 1.4% = 7万円
となり、合計で年間28万円の固定資産税がかかることになります。ただし、後述する軽減措置が適用されると、この金額からさらに減額される可能性があります。特に、居住用の住宅の場合、土地には「住宅用地の特例」が適用され、税負担が大幅に軽減されることが多いです。
新築住宅との違いと課税通知書の見方
新築住宅の場合、一定期間、固定資産税の軽減措置が適用されます。新築から3年間、マンションなどの耐火建築物なら5年間(長期優良住宅の場合はさらに延長されるケースも)は、建物の固定資産税額が2分の1に減額される特例があります。しかし、中古住宅の場合、原則としてこの新築軽減措置は適用されません。
そのため、中古住宅の固定資産税は、新築軽減措置が終了した後の税額と比較して考える必要があり、購入時には新築時より税額が高く感じることもあるかもしれません。しかし、中古住宅はそもそも建物の評価額が築年数に応じて下がっているため、必ずしも新築より高額になるわけではありません。
毎年送られてくる「固定資産税・都市計画税納税通知書」には、ご自身の土地や家屋の評価額、課税標準額、税率、そして計算された税額が詳細に記載されています。特に目を向けたいのは、「課税明細書」です。ここには土地と家屋それぞれの評価額が明記されていますので、ご自身の財産がどのように評価されているかを確認する上で非常に重要です。もし内容に不明な点があれば、遠慮なく管轄の市町村の税務課へ問い合わせてみましょう。
このように、中古住宅の固定資産税は、土地と建物の評価額に基づいて計算されます。次章では、この評価額に大きく影響を与える「築年数」と「リフォーム」について、さらに詳しく見ていきましょう。

築年数・リフォームが固定資産税に与える影響
中古住宅を購入する際、築年数の古い物件は購入価格が手頃になりやすい一方で、「固定資産税はどれくらいかかるの?」と疑問に感じる方もいるでしょう。また、自分たちのライフスタイルに合わせてリフォームを検討する方も多いはず。実は、築年数やリフォームの内容は、固定資産税に大きな影響を与えます。ここでは、その仕組みを具体的に解説し、あなたのマイホーム計画に役立つ情報をお届けします。
築年数と建物の評価額の関係
建物の固定資産税評価額は、築年数が経過するにつれて減少していくのが一般的です。これは、固定資産税評価基準に定められている「経年減点補正率」という指標が関係しています。
建物の評価額は、「再建築費(同じ建物を現在の資材や物価で再建築するのにかかる費用)」をもとに算出されます。しかし、建てたばかりの建物と、数十年経った建物では物理的な劣化が進み、その価値は下がっていきますよね。この劣化を考慮するために、再建築費に経年減点補正率を掛けて評価額を算出するのです。
経年減点補正率は、建物の構造(木造、鉄骨造、RC造など)や用途(住宅、店舗など)によって異なり、年数が経つごとにその数値が下がっていくように設定されています。例えば、木造住宅の場合、新築時を1.0とすると、20年、30年と経つにつれて徐々に0.2程度まで下がっていくイメージです。ただし、評価額が全くのゼロになることはなく、最終的にはある程度の「残存価値」が評価されることになります。一般的に、木造は約20~25年、鉄骨造は約30~40年、RC造は約60年程度で、評価額の下落が緩やかになると言われています。
築年数による評価額の具体的な減価シミュレーション(イメージ)
仮に、再建築費が1,500万円と評価される一般的な木造住宅があったとします。経年減点補正率の目安を用いてその評価額の変化を見てみましょう。
- 新築時:1,500万円 × 1.0 = 1,500万円
- 築10年時:1,500万円 × 0.5程度 = 750万円
- 築20年時:1,500万円 × 0.3程度 = 450万円
- 築30年以降:1,500万円 × 0.2程度 = 300万円(※残存価値として一定評価)
これはあくまで概算のイメージですが、築年数が古い中古住宅ほど、建物の固定資産税評価額は低くなる傾向にあり、それに伴って固定資産税額も安くなることが理解できるでしょう。ただし、土地の評価額は建物とは独立して評価されるため、築年数によって変動することはありません。もし、築年数がとても古いのに家屋の固定資産税が高いと感じる場合は、リフォーム歴など、何か特別な要因があるかもしれません。
リフォームが固定資産税に与える影響
中古住宅の魅力の一つは、自分たちのライフスタイルに合わせて自由にリフォームできる点ですよね。しかし、リフォームの内容によっては固定資産税評価額が上がり、結果として税額が増える可能性があります。どのようなリフォームが評価額に影響するのか、事前に把握しておくことが重要です。
評価額が上がる可能性のあるリフォーム
固定資産税評価額が上がるのは、建物の「構造」や「用途」、「性能」が大きく変わるようなリフォームです。具体的には以下のようなケースが挙げられます。
- 増築: 床面積が増えるため、その増えた部分が新たに評価対象となります。当然、評価額は上がります。2階建てを3階建てにするような大規模な増築は、特に影響が大きくなります。
- 用途変更: 例えば、一部を店舗や事務所として使っていた部分を、すべて居住スペースに変更する場合など、建物の用途が変わると、評価基準が見直されることがあります。
- 大規模な間取り変更: 壁を取り払って広いリビングにするなど、建物の骨格に関わるような大規模な間取り変更や、複数戸の住宅を一体化するようなリフォームの場合も、構造的な評価が変わることがあります。
- 高機能設備の新設: エレベーターの設置や、高性能な空調システムの導入など、建物の価値を高める特定の大規模設備の新設が評価対象となる場合があります。ただし、一般的なバス・トイレの交換やシステムキッチンの導入程度では、固定資産税が上がることはほとんどありません。
これらのリフォームを行った場合、自治体側で家屋の再調査が行われることがあります。リフォームによって建物の価値が向上したと判断されれば、翌年以降の固定資産税が増額される可能性があるのです。特に、建築確認申請が必要となるような増改築は、自治体が情報を把握しやすいため、評価額の見直しにつながりやすいでしょう。
評価額に影響しないリフォーム
一方で、ほとんどの一般的なリフォームは、固定資産税評価額には影響しません。これらは、建物の「価値を高める」というよりも、「快適性や機能性を維持・向上させる」ためのものと判断されるためです。
- 内装の修繕・交換: 壁紙の張り替え、フローリングの張り替え、建具の交換など。
- 設備の交換: システムキッチン、ユニットバス、トイレ、給湯器の交換など。
- 外壁塗装・屋根の葺き替え: 建物の外観や防水機能を保つための工事。
- エアコンなどの家電設置: 取り外し可能な設備は固定資産税の対象外です。
このようなリフォームは、毎日を快適に過ごす上で非常に重要ですが、固定資産税の心配をする必要はほとんどありませんのでご安心ください。ただし、大規模な増改築や、既存の基礎部分を改修するような工事には、確認申請が必要になる場合があります。その際は必ず専門家や自治体に相談し、適切な手続きを踏むようにしましょう。
リフォームの計画段階で「これは固定資産税に影響するのかな?」と疑問に感じたら、まずはリフォーム業者や建築士に相談したり、管轄の自治体の税務課に問い合わせてみるのが最も確実な方法です。

中古住宅の固定資産税を賢く抑えるポイント
中古住宅の固定資産税は、築年数やリフォームによって変動しうることがお分かりいただけたでしょうか。しかし、ただ税金を支払うだけでなく、賢く税負担を軽減できるポイントがいくつかあります。特にマイホーム計画初心者の方は、少しでも家計の負担を軽くするために、ぜひこれらの情報を活用してください。子供たちの教育費やレジャー費用のためにも、税金を最適化することは非常に重要なことです。
軽減措置を正しく理解する
固定資産税には、特定の条件を満たすことで税額が軽減される措置があります。中古住宅でも適用される可能性のある主な軽減措置は以下の通りです。
住宅用地の特例
これは、固定資産税において最も大きな軽減効果をもたらす特例の一つです。住宅が建っている土地(住宅用地)に対して適用され、土地の税額が大幅に軽減されます。
- 小規模住宅用地: 200平方メートル以下の住宅用地に対し、課税標準額が6分の1に軽減されます。例えば、150平方メートルの敷地に家がある場合、土地の評価額が3000万円であれば、課税標準額は3000万円 × 1/6 = 500万円として計算されます。
- 一般住宅用地: 200平方メートルを超える住宅用地の部分に対し、課税標準額が3分の1に軽減されます。例えば、300平方メートルの敷地であれば、最初の200平方メートルは小規模住宅用地として6分の1、残りの100平方メートルは一般住宅用地として3分の1の軽減が適用されます。
この特例は、中古住宅であっても、居住用として使用されていれば自動的に適用されることがほとんどです。しかし、将来的に自宅敷地の一部を駐車場として分離したり、非住宅用の建物を建てたりすると適用対象外となる場合があるため注意が必要です。
特定の改修工事による減額措置
中古住宅を購入した後、一定の条件を満たすリフォームを行った場合、建物部分の固定資産税が一定期間減額される特例があります。これらは、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修が主な対象です。
- 耐震改修: 1982年1月1日以前に建築された住宅で、現行の耐震基準に適合させる改修工事を行い、自治体による証明を受けた場合、固定資産税が1年間(長期優良住宅化改修の場合は2年間)2分の1に減額されます。工事費の条件(50万円以上など)があります。
- バリアフリー改修: 65歳以上の高齢者が居住する住宅などで、廊下の拡幅、階段の手すり設置、段差解消などのバリアフリー改修工事(工事費50万円以上など条件あり)を行った場合、固定資産税が1年間3分の1に減額されます。
- 省エネ改修: 窓の断熱改修、天井・壁・床の断熱改修、太陽光発電設備設置など(工事費60万円以上など条件あり)を行い、自治体の証明を受けた場合、固定資産税が1年間3分の1に減額されます。
これらの特例は、それぞれ適用要件や減額割合、減額期間、申請期限が細かく定められています。また、複数の特例が重複して適用されることは原則ありません。リフォームを検討する際は、これらの減額措置が利用できるか、そしてその要件を満たせるかについて、事前に自治体の税務課やリフォーム業者に確認することをおすすめします。多くの場合、工事完了後3ヶ月以内に申請書と必要書類を提出する必要があります。
評価額に疑問がある場合の対処法
毎年送られてくる固定資産税の納税通知書を見て、「この評価額は本当に適正なのかな?」と疑問に感じることもあるかもしれません。特に中古住宅の場合、以前の所有者がどのような使い方をしていたかなどで、評価額の背景が分かりにくいこともあります。もし評価額に疑問を感じたら、以下の方法で確認や異議申し立てが可能です。
- 課税台帳の閲覧: 納税義務者は、納税通知書が届く時期(通常は4月から6月頃)に、自分の固定資産の評価額が記載された「固定資産課税台帳」を、管轄の市町村役場の税務課で閲覧することができます。他の類似する土地や家屋との比較を通して、自分の土地や家屋の評価が適正かどうかの判断材料にできます。
- 固定資産評価審査委員会への審査の申出: 課税台帳の評価額に不服がある場合、納税通知書を受け取った日から3ヶ月以内であれば、「固定資産評価審査委員会」に対して審査の申出を行うことができます。これは専門の委員会が評価の適正性を審査する制度です。申出の際には、評価額が不適正であると考える具体的な根拠を提示する必要があります。
- 不動産鑑定士への相談: より専門的な視点から評価の妥当性を判断したい場合は、不動産鑑定士に相談し、鑑定評価を依頼することも一つの手です。ただし、鑑定には費用がかかるため、固定資産税額との費用対効果を十分に考慮する必要があります。
安易に評価額に異議を唱えるのではなく、まずは自治体の税務課に相談し、評価の根拠を詳しく説明してもらうのが第一歩としておすすめです。
中古住宅購入時のチェックポイント
中古住宅の固定資産税は、新築時ではなく、現在その物件が持つ価値によって決定されるため、購入前に税額の目安を把握しておくことが重要です。以下の点をチェックすると良いでしょう。
- 重要事項説明書での確認: 不動産会社から渡される「重要事項説明書」には、売買対象となる物件の固定資産税額が記載されていることがほとんどです。これは、売主が前年に実際に支払った税額ですので、最も現実的な目安となります。ただし、年間の税額が示されている場合は、土地・建物それぞれの評価額も確認しておくと、将来的な判断に役立ちます。
- 売主や不動産会社に確認: 重要事項説明書に具体的な税額が記載されていない場合や、より詳細な情報が知りたい場合は、売主や不動産会社に過去の固定資産税の納税通知書を見せてもらうか、金額を教えてもらうよう依頼してみましょう。築年数やリフォーム歴が分かれば、売却時の状態での評価額の目安が把握できます。
- 自治体への問い合わせ: 購入前の物件は、個人情報保護の観点から、買主候補者が直接自治体に評価額を問い合わせることは原則できません。しかし、売主から委任状をもらえれば可能な場合や、不動産会社を通じて評価証明書を取得してもらうことができる場合があります。
住宅ローンを組む際には、毎月の返済だけでなく、固定資産税や火災保険料、修繕費などのランニングコストも考慮に入れた無理のない資金計画を立てることが何よりも大切です。固定資産税は毎年必ずかかる費用なので、事前にしっかりと把握し、家計に大きな影響を与えないか確認しておきましょう。特にお子様の教育費や日々の生活費など、将来にかかる費用と合わせて考えることで、より安心してマイホーム計画を進めることができるはずです。
結論・まとめ
マイホーム計画を進めるあなたにとって、中古住宅の固定資産税がいかに重要な要素であるか、そしてその税額が築年数やリフォームによってどのように変わるか、深くご理解いただけたことと思います。改めて、今回の重要なポイントを振り返りましょう。
まず、固定資産税は土地と建物の「固定資産評価額」に基づき、標準税率1.4%で計算されます。この評価額は、築年数が経つにつれて建物の価値が経年減点補正率によって下がっていくため、一般的に古い中古住宅ほど建物の固定資産税は安くなる傾向にあります。しかし、土地の評価額は独立しており、築年数では変動しません。
リフォームについては、増築や大規模な間取り変更など、建物の「構造」や「用途」に影響を与えるような工事は固定資産税が上がる可能性があります。一方で、壁紙の張り替えや設備交換といった一般的な内装リフォームは、ほとんど税額に影響しませんのでご安心ください。リフォーム計画の際は、税金への影響も考慮して内容を検討することが大切です。
そして、最も大切なのは、軽減措置を上手に活用することです。特に「住宅用地の特例」は、居住用の土地であれば自動的に課税標準額が大幅に軽減されるため、中古住宅の固定資産税を考える上で非常に大きな要素となります。また、耐震改修やバリアフリー改修、省エネ改修を行った場合には、一定期間建物の固定資産税が減額される特例もありますので、要件を確認し、積極的に活用を検討しましょう。
マイホームの購入は、住宅ローンの返済だけでなく、固定資産税や修繕費といった年間にかかる費用全体を考慮した資金計画が不可欠です。特にお子様の成長や教育費なども見据え、「無理のない返済計画」と「余裕のある維持費の確保」が、家族が安心して暮らせるマイホーム生活の秘訣です。中古住宅の固定資産税は、事前に情報収集を行い、賢く計画を立てることで、けっして恐れるものではありません。
この記事を通じて、あなたが中古住宅の固定資産税に関する不安を解消し、自信を持ってマイホーム計画を進められることを心から願っています。さあ、理想のマイホーム、そして素敵な家族の未来に向けて、一歩を踏み出しましょう!
関連記事
-

-
賢く活用!住宅ローンと併用できる補助金制度の探し方ガイド
2025/08/21 |
マイホーム購入は、人生の一大イベントであり、同時に大きな決断ですよね。お子様たちの成長と共に「やっ...
-

-
日当たり・地盤・周辺環境…理想を叶える土地選び完全ガイド
2025/08/07 |
マイホーム計画、家族みんなの夢が詰まった一大プロジェクトですよね。特に「どんな家を建てよう?」と想像...
-

-
子ども部屋のレイアウト決定版!専門家が教える失敗しない間取りと家
2025/09/24 |
子ども部屋のレイアウトは、子どもの成長とともに変化する空間づくりの難しさがあります。特に、これから...
-
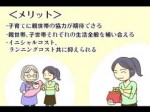
-
二世帯・大家族で住む家のメリット・デメリット
2020/03/07 |
二世帯・大家族で住む家をお考えの皆さんへ、二世帯・大家族で住む家をつくる際のメリット・デメリットと失...











