働き方改革に対応!工務店の労働時間削減と生産性向上
公開日:
:
工務店 経営
近年、建設業界を取り巻く環境が大きく変化しています。特に工務店では、長時間労働や人手不足、業務効率の低下など、多くの課題が指摘されています。こうした中、「労務管理」の精度向上と「働き方改革」への対応が急務となっています。本記事では、現場の実情を踏まえたうえで、工務店が実践できる労務管理の具体策と、働き方改革による生産性向上の方法を体系的に解説します。読者の皆さまが日々感じている「労働時間をどう削減するか」「現場と事務の両立をどう最適化するか」といった疑問や不安を解消し、今すぐ実行に移せる実践的なノウハウをお伝えします。この記事を読むことで、御社独自の未来志向の職場づくりへの確かな一歩が踏み出せます。
働き方改革の「実践的」導入戦略:基礎から応用まで
工務店にとって、働き方改革の流れに対応するためには、まず現場の現実と自社体制の「見える化」が出発点となります。ここでは、労務管理の基礎事項の整理から、すぐに着手できる改革手順まで、段階的な導入戦略をご紹介します。
現状分析と課題抽出から始める
- 勤務実態を正確に記録するまず、従業員一人ひとりの勤務時間、残業状況、休憩・有給取得実態などを正確に把握する仕組みを整えます。タイムカードや勤怠管理システムを導入し、現場・事務所ともに労働時間を見える化しましょう。紙の記録に頼らず、クラウド勤怠管理サービスの活用もおすすめです。
- 「残業が発生する理由」を特定する作業別・部門別に「なぜ残業が必要となるのか」を徹底的に洗い出してください。一例として、朝晩の準備作業、材料運搬、書類作成、待ち時間、突発対応などがあります。現場単位でヒアリングを実施し、現実的な課題を抽出しましょう。
- 経営陣・管理職・従業員へのヒアリング定性的な課題も含め、経営層から現場スタッフまで幅広い意見を集めます。「どこにムダがあるのか」「どのように働ければよいか」など、コミュニケーション重視の聞き取りを行うことで、現場の納得感も醸成できます。
- 「働き方改革」計画の作成・目標設定課題が見つかったら、具体的な働き方改革計画を策定しましょう。例えば、1ヶ月あたりの残業削減目標、定時退社日設定、労働時間の上限ルール明文化、週休2日制の導入など、可視化できる目標を掲げます。進捗管理表やロードマップを作成して、業務効率化の道筋を明確にしましょう。
現場で使えるアクションプラン
- 業務プロセスの標準化・マニュアル整備職人に属人化しがちな作業内容を見直し、標準手順や作業マニュアルを作成します。作業ごとの「標準時間」を設定し、誰が担当しても品質・スピードが一定になる環境を整えます。OJTや現場勉強会も有効です。
- ITツール・システムの導入工事台帳、発注・在庫管理、工程表の作成、勤怠管理など、日々の管理業務にはIT化が効果的です。無料から使えるクラウドサービスも多数あり、現場写真の共有や報告業務の効率化も期待できます。まずは「一番面倒な業務」からIT化してみましょう。
- 業務の外注・アウトソーシング活用自社内で抱え込みすぎている業務(設計図作成、経理、書類整理など)は、外部の専門業者や事務代行に一部委託することも重要です。コストと業務効率のバランスを見ながら、内製と外部活用を十分検討してください。
- ノー残業デー・有給取得の推進月1回以上の「ノー残業デー」設定や、有給休暇の積極取得を推奨します。リーダー自らが率先し、会社としての姿勢を明確にしましょう。制度だけでなく、取得しやすい雰囲気づくりもセットで考えます。
具体例:労務管理導入前と導入後の違い
例えば労務管理システムを導入したA工務店では、工事現場ごとにスマホで出退勤を打刻する運用に切り替えました。作業日報の入力もWEBで完結。毎月の勤怠集計や時間外労働のチェックが自動化され、従業員の「申告ミス」や「紙の記入漏れ」が激減、結果として年間200時間以上の事務作業時間を削減しています。このように、労務管理の仕組み化・可視化は、業務効率化と働き方改革を同時に推進する最初の一歩となります。
労務管理×働き方改革:成果を最大化する具体的な取り組み
働き方改革を着実に工務店へ定着させるためには、「形だけ」ではない実効性が求められます。本章では、業界特有の事情に合わせた労務管理と働き方改革を組み合わせる、具体的な施策・ツール・コミュニケーションの設計方法について解説します。また、実際に社内から挙がりやすい疑問やFAQにもお答えしますので、現場導入時の参考にしてください。
成果を出すステップ式アクションプラン
- 「業務のムリ・ムダ・ムラ」を徹底的に洗い出す長時間労働の温床となる業務の重複や非効率、役割のあいまいさを炙り出します。工程会議や作業日報、現場リーダーとのディスカッションを通じて、現状の業務フローにメスを入れましょう。チェックリストや業務フローチャートの作成も効果的です。
- ICT/DXによる情報共有・効率化社内LINEやグループウェア、現場専用スケジューラー、写真・資料共有システムなどを導入し、口頭や紙・FAXに頼っていた情報のやりとりをデジタル化します。全員がタイムリーに情報を把握できることで、現場の待ち時間やミスが大幅に減ります。ITツールが苦手な従業員には、OJTやマニュアルを作成し、段階的に浸透させていきましょう。
- 人員配置・シフトの最適化効率的な人員配置には、繁忙期・閑散期の業務量変動や、多能工化の推進がカギです。担当作業をスキルマップで見直し、A現場、B現場で働くスタッフも相互フォローできる体制を整備します。月単位・週単位でのシフト見直しを徹底しましょう。
- 評価制度・インセンティブ設計単に労働時間を短縮するだけではなく、成果やプロセスを評価し、インセンティブを明確にします。例えば、「定時退社日や有休取得を達成した場合の手当支給」「業務効率化への貢献を表彰」等、工務店独自の評価基準を設置しましょう。現場が納得できる基準であることが重要です。
- コミュニケーションの質向上とボトムアップ体制管理職と従業員、現場と本部の間で気軽に意見交換できる仕組み(定例ミーティング、意見募集BOXなど)を構築します。トップダウンだけでなく、実際に現場からの課題提起・解決案を積極的に吸い上げる風土を作ることで、働き方改革の現場定着が進みます。
よくある疑問と解決策Q&A
- Q1:現場ごとに働き方や業務量が違うので、労務管理の標準化は現実的ですか?A:完全な画一化は難しいですが、「タイムスタディ」や作業分析を活用することで、現場ごとの標準モデルを作ることは可能です。工種別、工期別に「モデルシフト」「モデル工程表」を作成し、大きな枠組みでの標準化を目指しましょう。
- Q2:IT化・システム化に抵抗感が強い社員がいます。どうやって現場に定着させればいいでしょうか?A:一気に大規模導入せず、「一番困っている業務」から部分的にITツールを導入するのが有効です。現場にヒアリングし、負担感が少ない部分から成功体験を作ることで、「使うとラクになる」と納得してもらいやすくなります。OJTや先輩社員のサポートも欠かせません。
- Q3:労働時間短縮が進むと、従業員の給与が減るのでは?A:残業手当など一部の収入が減るケースもありえますが、基本給やインセンティブ制度の見直しで、「効率化・品質向上に貢献した分」をきちんと評価する仕組みを導入しましょう。生産性が上がれば会社としても収益が向上し、長期的には全体の給与水準UPへと繋がります。
- Q4:法令改正や36協定、働き方改革関連法案にどう対応すればよい?A:最新の労働法規や36協定の内容を必ず確認し、就業規則・賃金規定の見直しを行いましょう。社会保険労務士や外部専門家との定期的な連携、研修の開催も有効です。社内に正しい知識を伝え、随時アップデートできる体制構築を目指しましょう。
中小建設業・工務店での事例紹介
B工務店では勤怠管理と工程表作成をクラウドシステムで統合管理し、「午前1回・午後1回の現場ミーティング+全員LINE報告体制」を運用しています。小規模事業者でもシステム化のハードルは年々下がっており、スモールスタートからでも充分な効果が生まれています。現場スタッフ自身が「効率化で自分の仕事がラクになる」成功体験を積めること、その積み重ねが働き方改革最大の近道です。
労務管理を継続的に成功させるための「次の一手」
働き方改革を一過性の取り組みで終わらせないためには、「継続的な可視化」と「改善サイクル」が不可欠です。この章では、労務管理の応用(PDCAの実践、効果測定)および、会社全体で取り組みを続けていくための組織体制と仕組み作りを、具体的に提案します。
ステップ1:定期的な振り返りとPDCAサイクル
- 毎月・四半期ごとの労働時間や業務効率指標を集計・チェックする勤怠データや残業時間、有休取得率、現場ごとの作業スピード等を定点観測します。問題点に気づいたら即座に改善アクションを起こすPDCA(Plan-Do-Check-Act)型の管理運用を徹底しましょう。
- 業務フローやマニュアルのアップデート現場スタッフからのフィードバックと実績データをもとに、作業手順や社内ルールを定期的にアップデートします。時代や業界の変化に柔軟に対応できる仕組み作りが、持続的な労務管理と働き方改革の基盤となります。
- ワークショップ・全社員参加型の意見交換会開催月次または年次で、全スタッフが集まるワークショップや意見交換の場を設けます。改善提案コンテストや社内表彰なども取り入れ、現場全体を巻き込んだボトムアップ型の風土を育てましょう。
ステップ2:数値化と効果測定で「やりっぱなし」を防止
- 労務管理KPIの設定残業時間、有給取得率、作業効率、生産性(売上高/労働時間)、安全管理指標など、自社に合ったKPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的に数値で進捗を比較・確認しましょう。
- 現場スタッフやパートナー企業とのコミュニケーション下請け企業や協力会社とも課題意識を共有し、合同ミーティングや情報共有ツールの導入を進めます。全社的な一体感を持つことが、働き方改革実現の要です。
- 外部リソース・専門家の活用難易度の高い法令対応、評価制度設計、新ツールの導入時には、社会保険労務士やコンサルタント、ITベンダーなど外部の専門家にサポートを依頼しましょう。自社では見えにくい「外部視点」を取り入れることが、継続的な成長の鍵となります。
ステップ3:働きがいと企業ブランドの向上
- エンゲージメント施策の推進モチベーション向上や働きがい醸成には、適正な評価・報酬、社内コミュニケーションの活性化が欠かせません。安心して長く働ける会社として、対外的な発信やリクルート活動にも積極的に取り組みましょう。
- 組織の柔軟性・多様性の確保女性や若手人材の積極活用、時短勤務やフレックスタイムの試験運用も行い、多様な働き手が活躍できる環境を整備しましょう。複数現場間での人材シェア、パート・アルバイトの有効活用も有効です。
これからの工務店経営者のための「労務管理」応用スタイル
工務店の規模や経営スタイルによって、最適な労務管理と働き方改革の施策は必ずしも一つではありません。上記の取り組み例から、自社に適した方法をカスタマイズし、進捗に応じてアジャイル(柔軟)に修正することを恐れないでください。経営者自らが「未来志向の働き方」を体現し続ける姿勢が、組織の継続力と可能性を飛躍的に高めます。
まとめ
工務店の労務管理および働き方改革は、単なる「労働時間削減」のための施策にとどまらず、事業全体の生産性・安全性・社員の働きがいを高め、持続的な成長を実現する原動力です。この記事でご提案した、現状分析からIT活用、評価制度やボトムアップの組織運営、そして継続的な効果測定に至る各ステップを、今すぐ貴社の現場でアクションプランとして落とし込んでください。一歩一歩着実に積み重ねることで、未来につながる職場の仕組み・企業ブランドが必ず形成されます。変革の中心に立ち、時代の先を行く経営者として、「自社らしい働き方」を全員で切り拓いていきましょう。継続こそ力―この実践が、御社の新しい未来をきっとつくり出します。
工務店の集客・営業ならジーレックスジャパン →ホームページはこちら
商品の差別化へ!制振装置はこちらから →耐震・制振装置
友達申請お待ちしてます! →代表浄法寺のfacebook
工務店のネット集客ならこちら →工務店情報サイト ハウジングバザール
関連記事
-

-
販管費を徹底的に見直す!工務店の利益改善術
2025/08/22 |
工務店の経営において、利益率の低下や経費の増大はよくある悩みです。「何度もコスト管理の仕組みを入れ直...
-
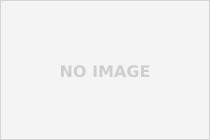
-
工務店 経営 注文住宅の電子契約化が進む
2023/11/14 |
パナソニック ホームズ(大阪府豊中市)は、新築工事請負契約の電 子化を同社支社13拠点での顧客との新...
-

-
経営理念を浸透させる!工務店の組織力強化
2025/09/03 |
工務店経営者が直面する最大の課題は、激化する地域競争や人材確保、職人不足、顧客ニーズの多様化など、多...
-

-
新しい資金調達!工務店のクラウドファンディング活用事例
2025/08/21 |
現在、地域密着型の工務店が生き残りと発展を図るうえで避けて通れない難題、それが資金調達です。近年、大...





























