事業譲渡で事業承継!工務店の選択肢
公開日:
:
工務店 経営
建設業界、とりわけ地域密着型の工務店は、堅実な経営とお客様との信頼構築が大きな強みです。しかし多くの工務店が「後継者不足」「経営者の高齢化」「将来の不安」といった課題に直面しているのも事実です。近年は、事業承継の手法も多様化し、親族内や従業員以外に第三者への事業譲渡という選択肢も注目されています。
この記事では、工務店経営者が現実的に活用できる事業承継、特に事業譲渡の具体的な手順、注意点、実践的な戦略をご紹介します。読者の皆様が、「どうやって自社のバトンを安全かつ円滑に渡せるのか」「事業譲渡でどのようなメリットや注意点があるのか」といった疑問を解消し、安心して事業の未来を託すためのステップバイステップの道筋を示します。この記事を読むことで、現実的な選択肢・行動指針が明確になり、事業承継への迷いが大きく減るでしょう。
事業譲渡の「実践的」導入戦略:基礎から応用まで
なぜ、事業承継の選択肢として事業譲渡が必要なのか
工務店の事業承継と言えば、従来は親族や幹部社員へのバトンタッチが主流でした。しかし少子高齢化や価値観の多様化により、「後継不足」という問題が加速しつつあります。その解決策のひとつが第三者への「事業譲渡」です。事業譲渡とは、事業活動の一部または全部を他企業や個人に譲り渡す方法であり、「会社そのものを売却するM&A」だけでなく「顧客基盤や従業員、設備だけを譲渡する」という柔軟な形も取り得ます。これにより、経営のバトンを確実かつスムーズに受け渡すことができるのです。
事業譲渡を検討する前に押さえておくべき5つのポイント
- 1. 自社の現状把握:
事業承継の第一歩として、「自社の強み・弱み」「経営状況」「財務状態」を整理しましょう。例えば売上推移、主要顧客、施工実績、従業員の定着率、所有不動産や車両の資産価値などを洗い出します。 - 2. 譲渡可能な資産と不可分な要素の仕分け:
何を譲渡対象とするか明確にします。例えば「顧客データ」「施工ノウハウ」「未完工事の契約」など譲渡可能なものと、「自身の職人技術」や「個人的信用」など不可分な要素の切り分けをしましょう。 - 3. 後継者または譲受先候補の洗い出し:
地元の関連業者、取引先、異業種の企業、またはM&A市場での第三者など、どこが内部・外部の候補になり得るかリストアップしてみます。 - 4. 譲渡後の影響評価:
経営権の移動による従業員や取引先の反応、事業の継続性、取引条件の変化などをシミュレーションします。このプロセスが円滑な事業承継を促進します。 - 5. 専門家との連携準備:
士業(中小企業診断士、公認会計士、弁護士など)やM&A仲介会社、銀行など、必要に応じて第三者のプロフェッショナルと早めに接点を持つことが重要です。
【ステップ実践】事業譲渡による事業承継の流れ
- ステップ1:現状診断と目標設定
事業承継のきっかけやゴール(引退時期、希望条件など)を具体的に書き出し、経営数字や顧客属性、強み・課題を客観的にまとめましょう。 - ステップ2:自社と事業価値の明確化
「どの部分に本当の価値があるのか」(例:地域ブランド力、リフォーム実績、職人ネットワーク等)を洗い出し、可能であれば簡易なバリュエーションを行ってみましょう。 - ステップ3:譲渡方式の検討
事業譲渡には「営業譲渡」「会社分割」「株式譲渡」などいくつかの手段があります。自社が完全譲渡なのか一部譲渡なのか、譲渡対象は何か明文化してください。 - ステップ4:譲受先リストアップと初期接触
相談先(地元企業、住宅関連業者、異業種)のリストを作り、「秘密保持契約(NDA)」締結後に概要を開示しましょう。 - ステップ5:条件交渉と基本合意書締結
論点は「譲渡価格」「従業員継続雇用」「業務引継ぎ期間」など多岐にわたります。プロのサポート下で交渉し、基本合意書(LOIなど)を締結します。 - ステップ6:デューデリジェンス(精査)と正式契約
財務や法務、労務状況の精査を受け、細かい条件調整の後、最終契約(事業譲渡契約書)とクロージングの日を設定します。 - ステップ7:引継ぎ・従業員/取引先対応
引継ぎスケジュールやマニュアルの用意、従業員・取引先向け説明会、関係者への丁寧な伝達とフォローアップが不可欠です。
【Q&A】事業譲渡で工務店が気になる疑問
- Q. 赤字でも事業譲渡で事業承継できますか?
A. 赤字だからこそ、「再生」「規模拡大」狙いで譲受希望者が現れることもあります。自社の資産やノウハウ、土地・建物などの強みをアピールできるよう整理しましょう。 - Q. 金融機関への返済や債務はどうなりますか?
A. 債務の承継可否や取引金融機関との協議は非常に重要です。譲渡対象から外す・債務引受を条件付けるなど、専門家に必ずご相談ください。 - Q. 社員・職人の雇用は守られますか?
A. 譲渡契約に「継続雇用」を盛り込み、双方で丁寧にコミュニケーションを取ることで安心感を提供しましょう。
事業承継×事業譲渡:成果を最大化する具体的な取り組み
「譲り先」を見極める実践的アクション
- 1. 地域密着企業・同業他社の精査:
地域に根差した電気工事会社や不動産業者、他の工務店など、「親和性」「将来性」のある企業リストをつくり、取引のある・なし問わず数社調査をしてみましょう。 - 2. M&A仲介・行政支援の活用:
地域の「事業承継・引継ぎ支援センター」や民間M&Aプラットフォームの無料相談・登録サービスを利用し、第三者への選択肢と具体的プロセスを確認します。 - 3. 理想の引継ぎ条件の事前整理:
可能な限り続けてほしい従業員、優先したい顧客、協力会社との関係など、譲渡条件の「優先度表」を事前に書き出し、交渉時の軸にします。 - 4. 守るべき文化・こだわりの可視化:
これまでの大切な経営哲学や店舗接客、施工へのこだわりも「目に見える形」にし、譲受側への継承を伝える工夫をしましょう。
事業譲渡における「高付加価値化」のコツ
- ・自社施工の特徴をマニュアル化・デジタル化(例:工程管理表、現場の安全教育写真、DX推進資料等)
- ・地域密着型で培った信頼やブランドストーリーを、数値や顧客アンケートで「見える化」する
- ・行政補助金や建設業許可、ISOなど「維持が難しい要素」もアピール材料へ転換する
成果を最大化するためのアクションプラン(ステップ形式)
- 事業承継推進プロジェクトの立ち上げ
経営者自身・後継予定者、外部士業や金融機関など、プロジェクトチームで「やるべきこと・スケジュール」を共有します。 - 譲渡候補への積極アプローチ
NDA締結後、「譲渡希望理由」「事業内容」「求める引継ぎ条件」等を簡潔な資料にまとめて定期的に情報提供します。 - 業務・財務デューデリジェンスの徹底
別紙の契約書整理、現場巡回チェックリスト、設備棚卸など、譲受先が安心できるよう細やかな情報開示を準備しておきます。 - 交渉・契約段階での専門家サポート活用
都度、専門家(弁護士、会計士、中小企業診断士)を交え、無理な条件・不利益な契約を避けるリスクヘッジを徹底します。 - 従業員・取引先向けの説明と調整
早い段階で従業員に伝え、不安払拭のための説明会や個別面談を実施し、離職リスクや業績低下を最小限に抑えましょう。 - 引継ぎ完了後の見守りとサポート
クロージング後も一定期間は経営アドバイザーとして関与し、心理的・実務的に引継ぎが軌道に乗るまで伴走できるとベストです。
【FAQ】実務担当・経営者が陥りやすい事業承継のお悩み相談
- Q. 事業譲渡で社名やブランドは残せますか?
A. 交渉次第で残すことも可能です。経営・事業の譲受形態に応じて、商号・ブランド・従業員の継続条件などを細かく設定してください。 - Q. 「のれん代」(営業権)はどのように決まる?
A. 「のれん代」は収益や独自の技術、受注残高、地域ブランドの評価などを元に、交渉で決まります。譲受側とメリットを共有できる根拠資料を準備しましょう。 - Q. 専門家に支払うコストは?
A. M&A仲介の場合は譲渡対価の数パーセントが一般的。行政窓口や商工会の無料サポートも必ずご検討ください。
事業承継を継続的に成功させるための「次の一手」
事業承継後も成長し続ける仕掛けを作るアクション
- 引継ぎマニュアル・ナレッジ共有システムの整備
施工管理資料やお客様リスト、社内の成功事例を整理し、後継者や譲受側に共有できる仕組みを作りましょう。 - 従業員の定着とモチベーション施策
定期面談や業績連動型インセンティブ、資格取得支援など、「引き継いだあと」にも組織の魅力を保てる施策を具体化してください。 - 外部支援活用によるキャッシュフローと経営管理の強化
金融機関、補助金支援、DX推進など、新体制での運営をサポートするネットワークを積極的に築きます。 - 継続的な目標設定と振り返りミーティング
半年・1年ごとに進捗を見直し、経営指標やブランド維持状況、顧客満足度をチームでチェックします。 - 地域とのつながり継続・新たな顧客開拓
地元イベント参画、市町村との協働プロジェクト、新築・リフォームといった事業多角化戦略も積極的に立案・実行しましょう。
【応用・事業承継の進化形】M&A後のシナジー・多角化攻略術
事業承継後、「譲渡先グループ」とのシナジーを活かすことで、受注拡大や新サービス展開も見込めます。例えば不動産部門の立ち上げやリフォーム専門店化、IoT住宅対応など、成長戦略を柔軟に描くのも一つの方法です。
お客様に「変わらない安心」をアピールしつつ、新しさ・独自色を取り入れることで、業績アップや地域社会への信頼構築に繋がります。これも、持続可能な事業承継の重要なアプローチです。
【Q&A】事業承継後の課題と解決法
- Q. 引継ぎ後の急激な売上減少が心配です…
A. ビフォー・アフターで顧客不安が高まることも。社内外に「新体制の強み」「顔ぶれ」を丁寧に発信し、安全・品質への“変わらぬ約束”を何度も伝えてください。 - Q. 後継者が自信を持ちきれません。
A. スモールステップで経営判断を任せ、成功体験を積み重ねてもらうことで、リーダーシップ形成を円滑にします。OB・OGや外部アドバイザーの声も活用しましょう。 - Q. 新体制での人材不足にどう備える?
A. 新規採用活動、外部協力会社とのネットワーク拡大、システム化による省力化モデルなどで持続性を高めていくのがポイントです。
まとめ
本記事では、工務店における事業承継と事業譲渡の全体像から、準備・実行・応用までステップバイステップで詳しく解説しました。読者の皆さまが抱える「次世代に安心して渡せるだろうか」「どうすれば従業員やお客様も守れるのか」「どの専門家や仕組みを頼れば良いのか」といった疑問に対し、具体的な手順と注意点を提示しています。
今すぐ始められる現状整理や譲受先リスト化、専門家への早期相談などのアクションによって、最良の事業承継が開けるはずです。将来の工務店や地域社会の発展に向けて、迷わず前向きに一歩を踏み出しましょう。今日からの行動が、貴社・従業員・お客様と地域の「安心な未来」へと必ず繋がっていきます。着実な準備と持続的工夫で「理想の事業承継」を実現してください。
工務店の集客・営業ならジーレックスジャパン →ホームページはこちら
商品の差別化へ!制振装置はこちらから →耐震・制振装置
友達申請お待ちしてます! →代表浄法寺のfacebook
工務店のネット集客ならこちら →工務店情報サイト ハウジングバザール
関連記事
-

-
競合との差別化を図るモデルハウス戦略
2025/10/07 | 工務店
工務店経営者の皆様、日々の経営、本当にお疲れ様です。競争が激化する現代において、お客様に選ばれ続ける...
-

-
従業員満足度が工務店の利益に直結する理由
2025/08/18 |
長引く人手不足や市場競争激化の中、工務店経営者の多くが「売上や利益の伸び悩み」「現場のモチベーション...
-

-
従業員が辞めない!工務店の離職率を下げる秘訣
2025/11/01 |
建設業界、特に工務店を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。慢性的な人手不足、熟練技能者の高齢化、...
-
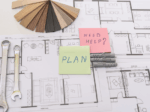
-
固定負債の適正化!工務店の財務健全化
2025/07/18 |
工務店を経営していると、日々の資金繰りや年度ごとの財務健全化に頭を悩ませることが多いものです。特に、...
- PREV
- 経費削減で利益を出す!工務店のすぐにできる対策
- NEXT
- 事業承継補助金を活用する!工務店の資金調達





























